前回は「算数を「出来ない」から「出来る」へ〜補助線のコツ・勘を磨く・「打ち込んだ点や円が波紋のように広がってゆく」イメージ・応用力を高める学び方〜」の話でした。
様々な視点から考える大事さ:類似の解法や考え方を展開
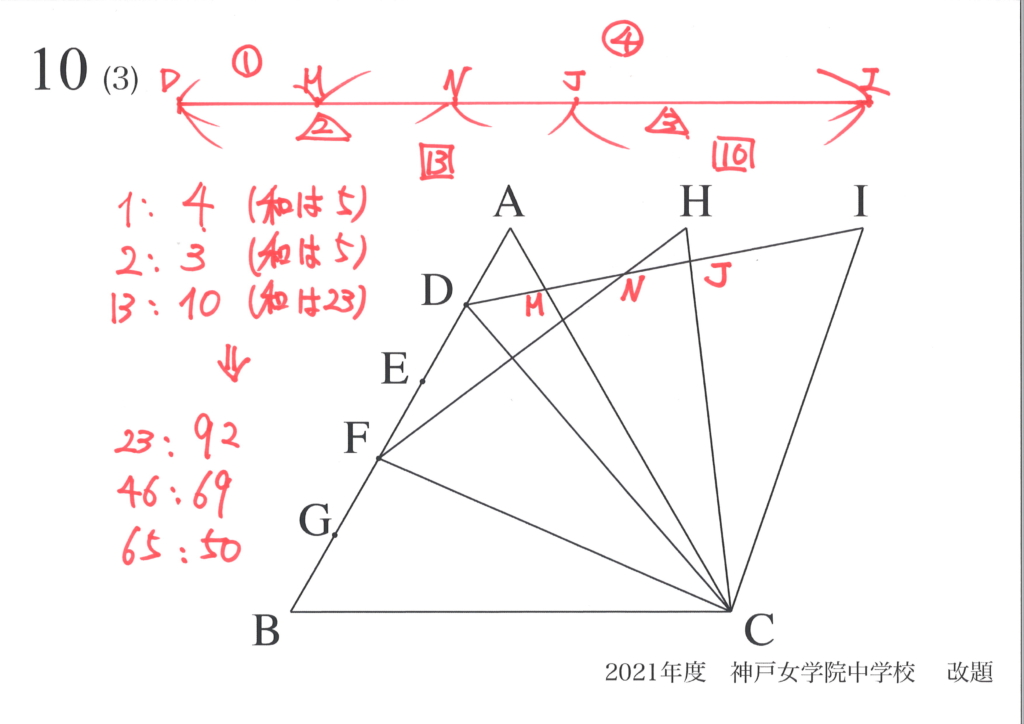
てんびん算に限らず、図形の問題等で同じ、似た解法・考え方を展開してゆくことは大事です。
その考え方をより深く吸収するきっかけになり、様々な展開をもたらすでしょう。
受験勉強をしていると、実に沢山の種類の問題があります。
それらを見て勉強していると、
 男子小学生
男子小学生こういう
問題もあるんだ・・・



こういうタイプの問題も
解けるようにならなきゃ!
沢山の種類の問題があり、それらを「一つずつマスターしてゆかなければならない」ように感じてしまいます。
すると、



キリが
ないよ・・・
このように「全部やるのは大変すぎる」と感じられる時もあるでしょう。
実に様々な問題が出題されていますが、多くの問題は「類似性」があります。
・ある解法や考え方で同じように解ける問題は、「一つの考え方」をしっかり固める
・少し切り口が異なる問題等は、絵や図を描いて解く
「一つの考え方」をしっかり理解して固めると、その考え方が展開します。
すると、類題は解けるようになるでしょう。
「同様の解法・考え方」や「少し異なる視点」で考える時は、「軸となる考え方」を意識しましょう。
思考力を増強:「軸となる考え方」を意識


「軸となる考え方」を意識するようになると、周囲に考え方が広がってゆくようになります。
子どもは沢山の問題を前に、それを解いてばかりいると、



こういう問題を
たくさんやらなければならないのか・・・



はあ〜
沢山ありすぎるよ・・・・・
このように「大変すぎる」と思う方が多いでしょう。
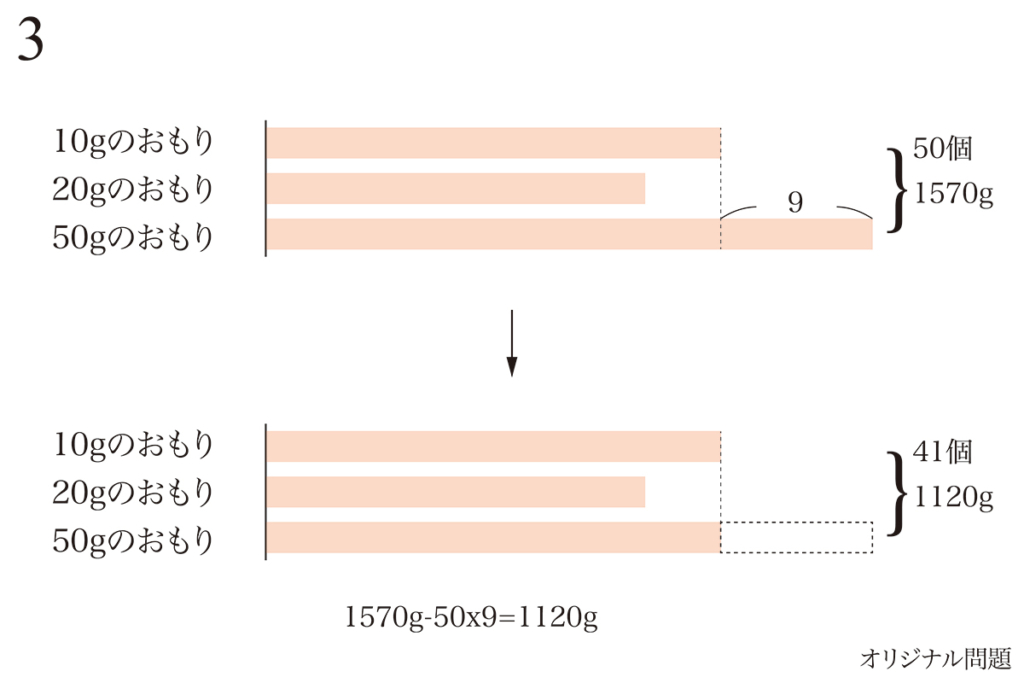

「たくさん類題を解く」ことで、学力を上げる勉強法もあります。
「たくさん解いて解法を暗記するように学ぶ」も大事な面があります。
それも良いですが、「別の視点」や「本質的な考え方」で学びましょう。
「暗記」ではなく「学ぶ・習得する」考え方です。(上記リンク)
問題を前に子どもが解いていて、理解に苦しんでいる時があります。



う〜ん・・・
ちょっと分からない・・・
子どもに、



ほら、その参考書・問題集の
解答に書いてあるでしょう。



それ読んで、
理解してみて。



でも、分からない
ことがあるんだけど・・・
親が一方的に「ひたすら勉強」と言うのは、出来るだけ避けると良いと考えます。
親も子どもと一緒に学ぶ:図や絵を一緒に描いてみる
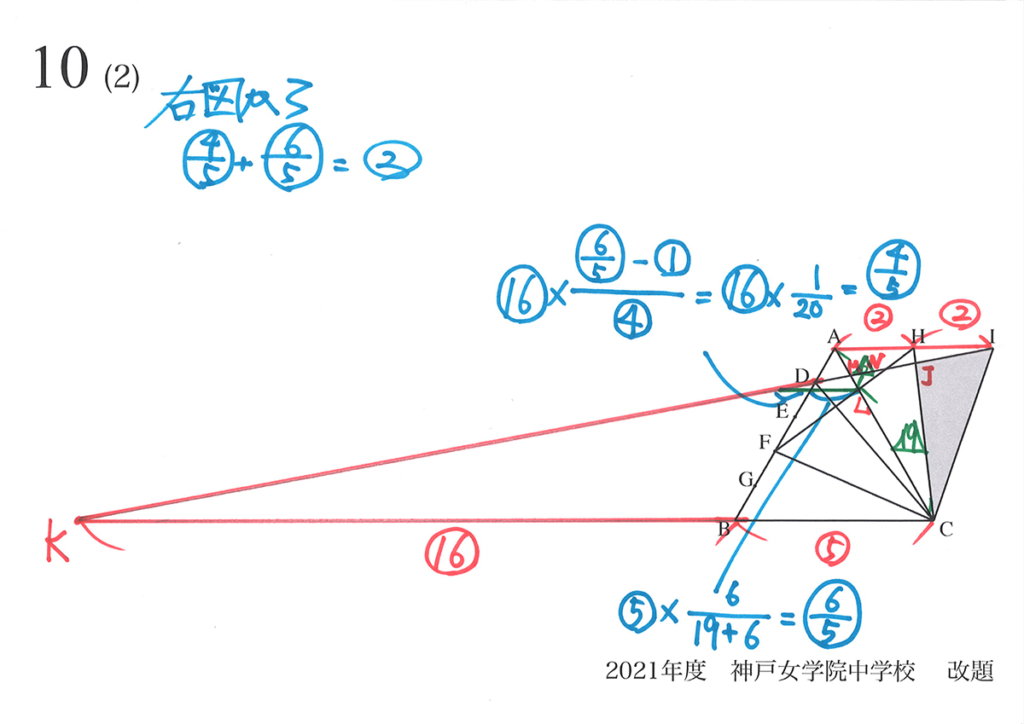

出来れば、子どもが勉強しているときに親も一緒に絵や図を描いて考えてみましょう。



ちょっと
一緒にやってみようか・・・



うん!
パパも一緒にやろうよ!
子どもと一緒に考えるのは貴重な経験です。
自分も一緒に考えてみれば、子どもが「どこがわからないのか?」がわかるようになります。



ああ、ここが
分からないんだね・・・
そうすると、子どもに「どう教えれば理解できるか?」が分かります。



ここは
こう考えてみたら・・・



そっか!
分かったよ!
子どもと一緒に考えた経験は、お互いにとって貴重な財産になります。
絵が上手に描けたり、字が綺麗でなくても良いです。
上手かそうでないか、よりも「一緒に描いて、一緒に悩む」ことが大事です。
子どもも喜び、学力が上がれば一石二鳥です。
ノートに丁寧に書かなくても良いでしょう。(上記リンク)
コピー用紙の裏でも書けるところに書いてみて、一緒に悩んでみましょう。
そして、子どもの学びへの意欲と理解力を大きく高めましょう。
次回は下記リンクです。




