前回は「中学受験生が塾に通い始める時期〜「いつから」と受験・初期に成績が劣る場合・じっくり学んで挽回・志望校の選択と子どもの「行きたい!」と強く思う気持ち〜」の話でした。
高校受験・大学受験と中学受験の大きな違い

高校受験・大学受験と中学受験は、かなり意味合いが異なると考えます。
最も大きな理由は、中学受験の先にある「中学校高校の6年間」です。
多くの中学では、中高一貫となっているため、中学受験の結果で進学する先の学校に、
 男子小学生
男子小学生僕は、これからA学園(中学・高校)に
6年間通うんだ!



私は、だいたい12歳から18歳を
B中学・高校で過ごすんだ!
中学と高校の教育は「義務教育の期間の境界」となります。
そして、高校の学びは中学の学びと大きく異なります。
中高の6年間の思春期における教育は、子どもへの影響が非常に大きいと考えます。
中高3年間ずつ、合計6年間の期間において



中学生の3年間と
高校生の3年間を過ごすんだ!
「同様に大きな影響を子どもに与える大事な期間」を過ごす中学校と高校。
多くの学校が中高一貫教育にある中、様々な教育理念があります。
その教育理念・教育内容にもよりますが、高校の3年間は「大学受験を意識せざるを得ない」期間です。
「高校から大学へエスカレーター」の学校は別です。
本来であれば、高校2年くらいまでは「学び」に集中して欲しいです。
そして、「その後1年〜1年半程度を大学受験の準備」が、教育上は望ましいでしょう。
現実的には、高校1年から多くの方が塾へゆき、多い方は高1で週に2〜3日程度塾に行きます。
そして、高校2〜3年では、家庭教師も含めると週4日以上塾・家庭教師となる方もいるでしょう。
中学校・高校での生活と大学受験


僕が高校生だった1990年代において、この「高校生は塾に多く通う」傾向がありました。
その後、中学受験において「通塾開始時期」が大きく低年齢化しました。
「小学校3年生から」は「当たり前」で、早い人は「小学校1年生から」となりました。
中学受験で多くの方が、4〜6年間を「受験対策の時期」として過ごして、



中学受験は
大変だった!
中学校へ入学する子が多いのが現実です。
そういう「受験対策期間が長かった」方は、



僕は、大学受験に対しても
早くスタートするんだ!



私も早めに
塾に行った方が良いかな?
当然、「大学受験に対しても同様」に考えるでしょう。
小さい頃に身についた習性は、なかなか変わらないものです。
すると、大学受験に対して、



中学受験と同じように、
4〜6年間が大学受験の準備期間!



中学一年から
塾に行った方が良いのかな?
このように考える方もいるでしょう。
中高6年間のうち「4〜6年間が大学受験の準備」となると、



結局、中高も
ずっと塾に行くのがいいのかな?
中高の期間ほとんどが「受験準備期間」となります。
これが思春期の子どもにとって「健全かどうか」は、様々な方の考え方があると思います。
「良い中学校・高校」とは?:「のびのび」教育+堅調な大学進学実績


「のびのび」の教育が良いことは、多くの方が同意すると思います。



うちの子どもが「のびのび」過ごすことは
とっても良いことだけど・・・



大学受験も
しっかり結果を出して欲しい!
一方で、「のびのびの教育」と「大学進学実績」の「どちらが大事か」は、様々な意見があるでしょう。
大学受験において「志望校(学部)に合格」か「志望校(学部)に不合格」かは、人生を左右します。
本人にとって、極めて大きな違いが生まれます。
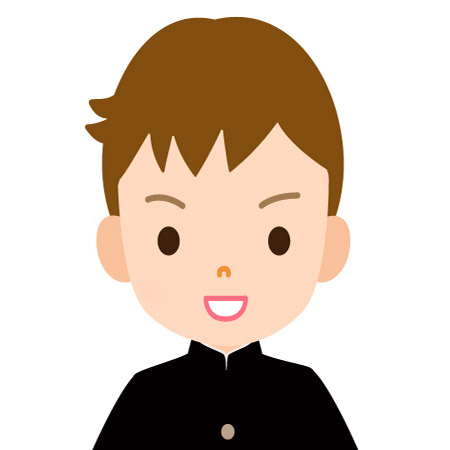
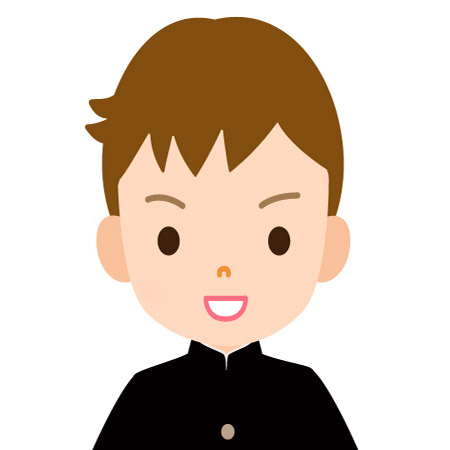

僕は弁護士になって、
様々な人を救いたい!
弁護士を目指す方は、法学部を目指すでしょう。
この時、「第一志望の法学部に合格する」ことが最も望ましいです。
「第二志望の法学部」でも弁護士になることは可能です。
そもそも、「受験資格がほとんどない」弁護士。
法科大学院制度が発足し、司法試験は完全に「新試験」に移行しました。
法科大学院に進学するためには、「法学部卒」が望ましいですが「法学部卒が必須」ではないです。



私は公認会計士に
なってみたいかな・・・
他に公認会計士・建築士などの国家資格がありますが、「卒業学部の要件」がない資格もあります。
一方で、「国家資格の受験資格」に「実務経験・卒業学部」が要件となることがあります。
例えば、



私は外科医になって、
手術で人を救いたい!
医師を目指す方は、日本の制度では「日本国内の医学部を卒業する」必要があります。
「第一志望の医学部」に合格できるかは別として、「医学部に合格しなければ、医師になれない」のです。
この観点から考える時、「子どもたち本人の将来像」に重大な影響を与えかねないのが大学受験です。
いかに教育理念が良くても、大学進学実績を「度外視する」姿勢はあり得ないでしょう。
一方で、日本のペーパー試験中心の大学受験対策は「近視眼的教育」になる可能性があります。





なぜ、「1+1=2」
なんですか?



またか!
うるさいな・・・



そう
「決まっている」んだ!



だから、
なんで?



もう、お前は
学校に来るな!



えっ?・・・
来ちゃダメなの?
小学校の先生から痛烈に罵倒されたエジソン少年は、小学校を退学することになりました。
エジソンとアインシュタインが少年だった頃の話を、上記リンクでご紹介しています。


「中卒」ですらなく「小卒」のエジソンは、膨大な先進的な発明・技術革新を成し遂げました。
「のびのび教育」の発想は、将来大きく伸びる可能性を持つと考えます。
中学校・高校において「のびのび本質的に学ぶ」と「大学受験のための勉強」をバランス良く学べる環境。
それこそが多くの保護者が望む環境であり、子どもたちにとって「良い中学校・高校」なのでしょう。
次回は上記リンクです。



