前回は「記述問題の対策・コツと積極的な気持ち〜記述問題の「良い文章」とは何か・記述を「勉強する」とは考えない姿勢〜」の話でした。
大人も難しい記述問題

記述問題に対して、中学受験生・高校受験生・大学受験生は、
 男子小学生
男子小学生なんだか
難しい・・・



記述問題の模範解答例って、
どうやったら書けるようになるのかな?



もっともっと、勉強して、
良い点がもらえるようになりたい・・・
このように悩む方が多いです。
そもそも「記述問題」は、大人でも難しいです。
例えば、歴史の問題で「吉田松陰」と答えたり、「正しいのはC」と答えるのは「学べば出来る」です。
「知っていれば」あるいは「暗記していれば」出来る問題です。
対して、「知っていること」は大事かも知れませんが、「決定打にはならない」のが記述問題です。



そう、だから
結局何を書けばいいんだろう・・・
大人だって、



この絵を見て
気づいたことを文章で書きなさい。
このように言われたら、



何を、どう文章に
書こうかな・・・
大抵の方は困ることが多いでしょう。
大人でも答えるのが難しい問題もあるのが、中学受験の記述問題です。
小学生が「きちんと正しい答えに至る」のは大きな困難があります。



そうなんだ・・・
大人でも難しいんだ・・・
社会人・大人でも難しいことが多い記述問題は、中学受験生の小学生が難しいと感じるのは当然です。
そこで、



難しい・・・
もっと勉強しないと・・・
記述問題を「もっともっと勉強」と考え過ぎない方が良いでしょう。
それよりも、記述問題を課す学校の過去問の文章を読んだり、解答例を書いてみて、



こういう風に
書けば良いのかな・・・



こういう視点も
面白いかも・・・
このように、記述の文章を楽しむ気持ちを持つと良いでしょう。
・出題された文章を「こういう視点もあるんだ」と楽しく読む
・自分の歴史・地理などの勉強の「一つのまとめ」として学ぶ
「正確な答え」が存在しない社会の記述への姿勢
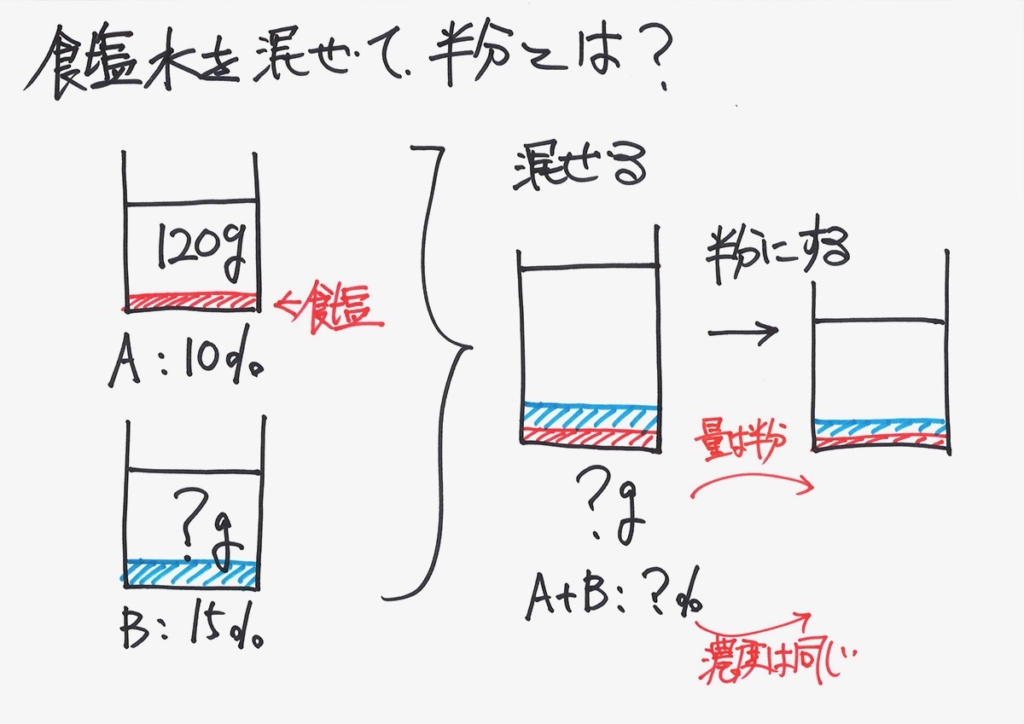

算数や理科の記述問題は、



答えだけではなく、
考える過程を見たい・・・



単なる答えだけではなく、
分かっている部分に点数を与え、評価したい・・・
このような中学校側・出題者側の考えがあります。
比較的答えがハッキリしている算数・理科は、「解くプロセスを表現すれば良い」と考えられます。



確かに算数や理科は、
「答え」に至る過程を書けばいいんだよね・・・



だから、算数や理科の記述は
出来そうな気がする・・・
武蔵中の理科「おみやげ問題」のように、「明確な答えがない」問題もあります。
それでも、理科の性質を書く以上は、「ある程度の答えの範囲がある」ことが多いです。
このように「ある範囲の答え」が想定されている時、全く見当違いのことを答えたら、



これは
違うんだよな・・・
書いても✖️になってしまうことが多いでしょう。
ところが、「ある範囲の答え」が想定されていていても、「他に考えようがある答え」に対しては、



これはちょっと違うんだけど、
そういう見方もあるかもな・・・
このように採点者が「ありうる」と感じるときは、



まあ、ちょっと違うけど
3点あげようかな・・・
このように「点数が与えられる」可能性があります。
算数や理科に対して、社会は「正確な答え」というのが存在しない場合があります。
「鹿鳴館の風刺画」がテーマの記述問題の考え方を、上記リンクでご紹介しています。
この問題は、比較的「ある程度考えられる答え」があります。
「共通すること」を答える場合、「何が共通しているか」を考えましょう。
・問題のヒントが隠されている
・「風刺した」など特徴的な言葉は「◯で囲む」や「下線を引く」で強く意識
この場合、対象が絵ですから



絵の中に
何かポイントがないかな・・・
このように「何かポイントがないかな」と考えましょう。
そうすると「鏡に猿が写っている」という重大なことに気づきます。
人間が写るはずの鏡に「猿が写っている」という状況です。



言われてみたら、
とっても変だね・・・
この「変な状況」は、比較的分かりやすいです。
ところが、焦ってしまうと「気づかない」可能性があります。
「自分なりの考えを表現」する姿勢


鹿鳴館の風刺画に関する問題で、「鏡に猿が写っている」ことに気づくことがポイントです。



気づかない時は、
どうしたら良いんだろう・・・
こういう問題は、



う〜ん、
分からない・・・
このように悩む前に、問題文にある絵をじっくり見るようにしてみましょう。
・理科実験のように、じっと観察
・「何らかの特徴」や「何かが変」に気づくように眺める
理科実験や観察問題を解くように、じっと絵や写真を見てみましょう。
そして、小さい頃にやった「間違い探し」を思い出すようにしましょう。



間違い探しって、
二つの絵の違いのこと?
未就学児〜小学校低学年の子どもが取り組む「間違い探しの絵」は、結構難しい時もあります。
同じように、



どこか違うところ、
変なところはないかな?
鉛筆を握って、「間違い」や「変な所」をマークすると良いでしょう。
何かヒントを見つけたら、その歴史的背景などを考えてみたら、答えやすいです。
模範解答は「一例」ですから、それをそのまま暗記するのは、あまり意味がありません。
詳しい採点方法は各校によるでしょうが、採点者は、



言いたいことは
分かるな・・・
あるいは、



大体の方向性が
合っているな・・・
こう考えるのであれば、◯にするでしょう。
学校の方針にもよりますが、「文章としての完成度」はあまり評価の対象ではないでしょう。
それよりも、「内容」が大事です。
この問題では、筆者なりに解答の一例を考えました。
・外面ばかり西洋化しても、内面は猿のようで猿真似に過ぎないこと
・洋服を着飾っていようと、外面と内面が乖離していて猿のように見苦しいこと
・自国の文化の大事な和服を、いとも簡単に捨て去るのは軽薄で猿同然ということ
・鏡に猿が映っているように、日本人の「表面的で急速な欧化」を猿同然と考えていること
解答欄の大きさや文字数などの制限にもよりますが、おおむね上のような内容で良いでしょう。
ここでキーワードは「猿」や「猿真似」です。
このキーワードを軸に、観察して分かったことを書くと良いでしょう。
この時「知識の断片」があることは、それはそれで良いですが、採点にはあまり関係ないでしょう。
あまり考えすぎずに大事なポイントを見つけたら、自分らしく書いてみる。
解答例を参考に「自分なりの考えを表現」して書いてみること。
これが記述式攻略への「最もシンプルな近道」です。
次回は下記リンクです。



