前回は「知識・暗記を効率良く上げる勉強法〜問題集を解いて脳に刺激・出題される具体的内容を学ぶ・性質などの暗記項目に対するイメージ・自分なりのイメージ・ぼんやりと理解する大事なプロセス〜」の話でした。
どんどんアウトプットする勉強法
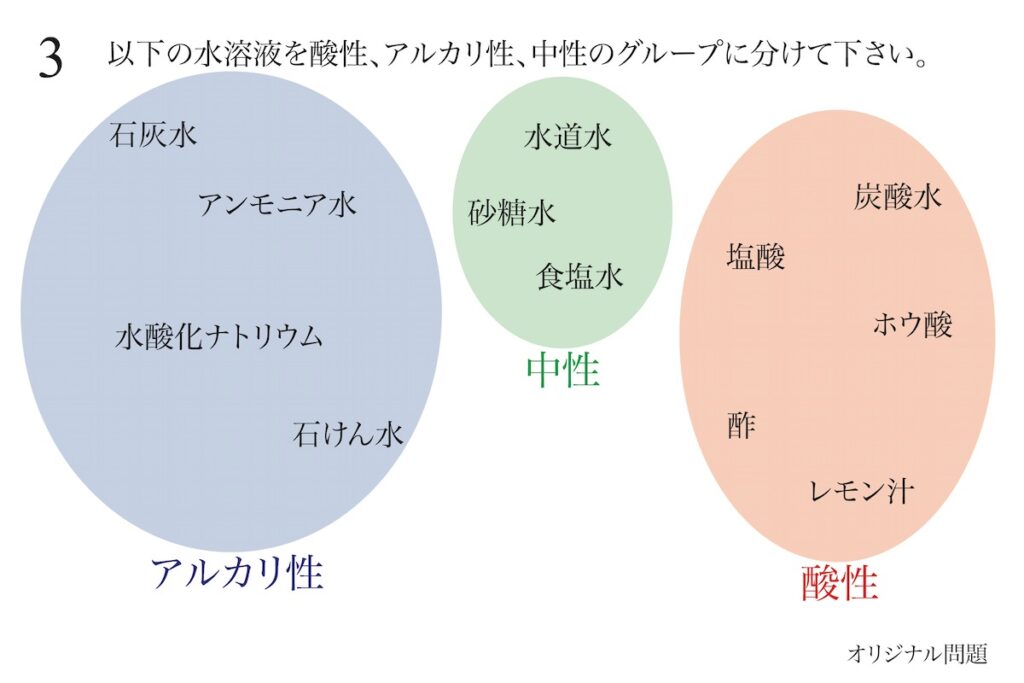
応用問題も暗記問題も、「問題集をどんどんやってみる」のが最も早く理解・暗記が進みます。
 男子小学生
男子小学生「問題集やる」のは
分かるけど・・・



やっても分からないと、
すぐ答えを見ていいの?
こう考える方も多いと思います。
「答えをすぐ見て、出来るだけ解法を覚える」という勉強の仕方もあります。
あるいは、「答えをすぐに見ないで、しっかり考えると頭に入る」という勉強法もあります。
「どちらが正しいか」というと、それぞれの勉強・試験に対する考え方次第になります。
筆者は、後者の「しっかり考える」立場です。



暗記も考え方も、どんどん覚えてしまった方が
良いのかな・・・



でも、なかなか覚えるのって、
大変で・・・



赤いシートで文字が消える問題集
やっているけど、なかなか頭に入らない・・・



それとも、しっかり参考書を理解することを
優先した方が良いのかな・・・
暗記にしても考え方にしても、「ある程度は覚える」必要があります。
「図形の補助線の考え方」に関しても、「基本となる定石」は頭に入れる必要があります。
補助線のコツに関する話を、上記リンクでご紹介しています。
この「頭に入れる」は「丸暗記」とは「似ているようで違う」と考えます。
「頭に入れる」のは、「丸暗記」よりも「もう少し考えて、理解して習得する」イメージです。
試験は「結局出来れば良い」面がありますが、「語呂合わせで丸暗記」は限界がありそうです。
・「丸暗記」よりも「もう少し考えて、理解して習得する」イメージ
・問題集をどんどんやってみて、「出題の構成」を理解して習得
選択肢・特定の答えを書く・記述式など、出題形式は様々です。
その中でも、「出題されやすい傾向」はあります。
そのような「傾向」は、参考書を読んでいるだけではなかなか出来るようになりません。
そこで、問題集をどんどん解いて「どんどんアウトプットする勉強法」をしましょう。
受験期中盤〜直前期は、全科目において参考書よりも問題集中心が良いでしょう。
自分の学び方の軸は変えない:勉強法も個性


受験生それぞれの学び方には、個性があります。
受験や学び方に関して、



こうすれば
成績アップする!



このように勉強すれば
偏差値が大幅に上昇する!
学力がアップする「ノウハウ」に関する話が、書籍やネットに溢れています。
そうした情報に触れると、



成績を上げるコツや
秘訣が学べる!
こう考えて、そうした他の方の成績アップ法を知りたくなる受験生が多いです。
筆者が中学高校生の頃は、今のように「ネットが当然」の時代ではありませんでした。
現代ではちょっと検索すると、無料で無限の情報が得られるネットには情報が氾濫しています。
それだけに「成績アップ法」を知ると、



自分も真似すれば
成績アップするだろう!
「自分も真似しよう」と考えてしまいがちです。



このように勉強すれば
偏差値が大幅に上昇する!
この「勉強法」は「その方にあった勉強法」であり、「他の方には合わない」可能性があります。
受験生は個性それぞれで、「合う勉強法もそれぞれ」です。
算数のおすすめ勉強法を上記リンクでご紹介していますが、「合う人」はご参考にして下さい。
ここまで自分がやってきた姿勢は変えずに進んでゆくのが良いでしょう。
直前期に模試の判定などが良くないと、



勉強のやり方が
悪いのかな・・・
「自分の勉強のやり方」に対する疑念が生まれることがあります。



違う参考書や
問題集をやってみよう!
こうして、新しい問題集を始めたり、他の塾へ行ってみたりして「改善を図る」考えはお勧めしません。
特に「他の塾へ行く、移る」のは最も良くないことで、「基本姿勢が変更」となります。
塾や先生それぞれで、「思考の軸」があります。
そして、習っている子どもは「その軸」に応じて学んでゆくのです。
「塾の先生や学んでいる参考書の軸」に「肉付けして強化してゆく」感じがベストです。
そこで、「新たな方法・考え方」に触れようとすると、基本的姿勢が揺らいでしまいます。
受験期中盤〜直前期は、姿勢は変えない方が良いでしょう。
・これまでの自分の学び方や塾の方針は、受験期中盤以降は変えないで堅持
・自分の学び方や塾の方針に合わせて、勉強を進化させる
苦手分野の暗記対策
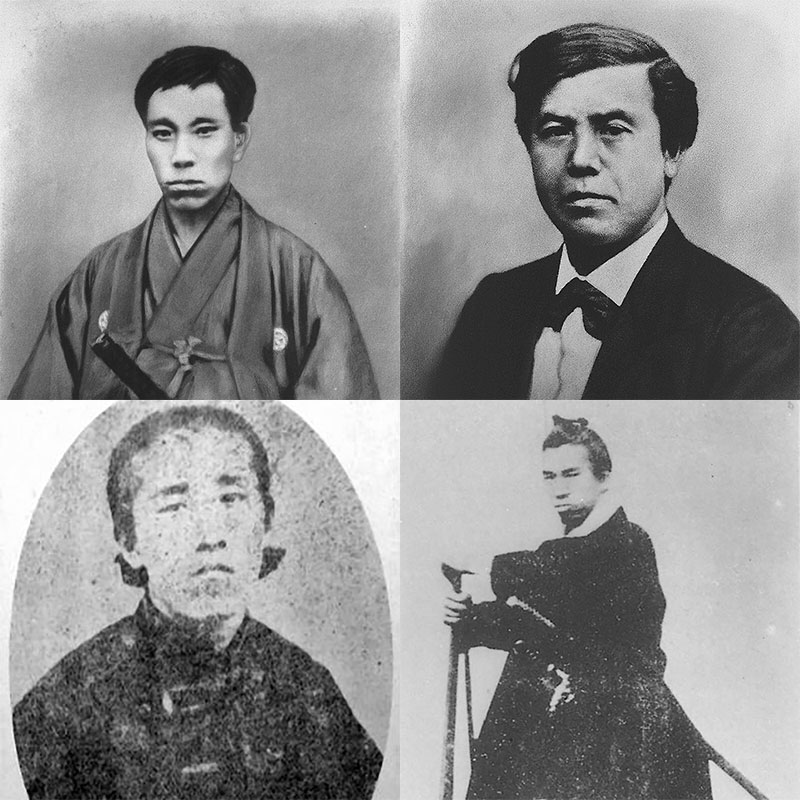

それでは、「どのように学力を強化するのか」です。
そして、受験期中盤以降は、時間がなくなってくるので「効率」が大事になります。
水泳の泳ぎ方と学びの話を、上記リンクでご紹介しています。
「効率的」というのは、本質的学びとは対極的な考えであります。
一方で、仕事でも勉強でも「効率」は非常に大事です。
効率が悪ければ、全体的なパフォーマンスも悪くなります。
そこで、学力を上げ、合格に近づくためには、効率を上げてゆくことに集中しましょう。
まずは、大勢の方が悩む「暗記の効率」です。
暗記は「ひたすら覚える」ことになりますが、「好きなことでない」場合は苦痛です。
自分が好きな分野であれば、「自然と頭に入る」のです。
ところが、好きでない場合はまるで「頭に入ることを拒否する」が如く、なかなか覚えられません。
歴史の人物や出来事は「歴史が好きでない」方にとっては、苦痛以外の何者でもないでしょう。
そこで、ある分野などで、



一気に
全部覚えよう!
「一気に暗記」を狙っても、「とても難しいこと」なので、



ここは、少しずつ覚えて
きたぞ!
自分が少しずつ「覚えてきた事」に目を向けましょう。



少しずつ
暗記が進んでいるんだ!
その「達成感」がやる気を持続して、学力増進につながるでしょう。
・キーワードを理解して、イメージを膨らませる
・反復演習する際に「覚えたこと」に着目して、達成感を感じながら学ぶ
・全体的な流れなどを「自分なりに理解」しながら覚える
そして、「暗記の効率アップ」は上記のようなことを意識しましょう。
次回は上記リンクです。






