前回は「「のびのびした賢さ」と「学ぶ力」を身につける姿勢〜テストの出来で責めない・「追い討ちをかけない」姿勢・「出来なかった」のは「出来るようにすれば良い」姿勢・体験する大事さ・育む「イメージする力」〜」の話でした。
子どもと一緒に虹をつくり出す体験

九州の五島へ家族と共に旅に行きました。
筆者も五島へ行くのは初めてで、海を渡って島へ船でゆくのは新鮮な体験です。
 内野吉貴
内野吉貴島から島へ、
船で渡るのは・・・



遊覧船とは全然違う
体験です。
旅先の宿泊先で、晴れた日に子供とシャワーを庭先にかけたら、虹が見えました。



あっ、
虹が見えるよ!



あっ、
消えちゃったよ・・・



あっ、
また虹が出てきた!
太陽光が燦々降り注いでいると、虹が見えることがあります。
色は何色見えますか。
見え方によって、赤、黄色などの色の位置は変わりますか。
そもそも、なぜ虹がみえるのでしょうか。
この理由は「散乱した水滴に光が乱反射してプリズム効果が出る」ことです。
この理由は大事ですが、「理由を知る」ことよりも「実体験する」方が大事だと考えます。
そういうことを子どもと遊びながら話すのは、親にとっては楽しいことです。
そして、子どもにとって、とても良い理科の勉強になります。
ちょっとした実験で、子どもと一緒に考える話を上記リンクでご紹介しています。
理科に限らず、なんでも



これは
何でだろう?
このように思って、少し考えてみる事は、大事な事です。
学びの好循環を生む「なぜ?」の好奇心


本を読んで勉強するのは、大事な事です。
本から学ぶことは「様々な世界を知る」ことで、子どもから大人まで最も大事なことだと思います。
一方で、



本に書いてあるから、
こうなんだ・・・
知識を丸暗記ばかりするのは、応用力が育たないでしょう。
ひらがなやカタカナなどは、「こういうものだ」と学ぶしかない面があります。
言語の学びなどは、場合によっては「暗記するしかない」面があります。
丸暗記が必要な時も、ただ漫然と丸暗記するだけではなく、



ここは
なぜだろう?
「なぜだろう?」を考えることも良いでしょう。
主体的に学ぶ姿勢を身につけると、子どもも勉強する・学ぶのが楽しくなるでしょう。
楽しくなれば、自分でやりたくなります。
好奇心を感じると大人も楽しいですが、子どもは最も好奇心に敏感です。
子どもが「何かを学ぶこと」に何らかの好奇心を発見した時。



これって
楽しいかも・・・
「楽しい→色々と分かるようになる→テストで点数が上がる→楽しい・・・・・」と好循環になります。
のびのびした賢さで学ぶ力を発展
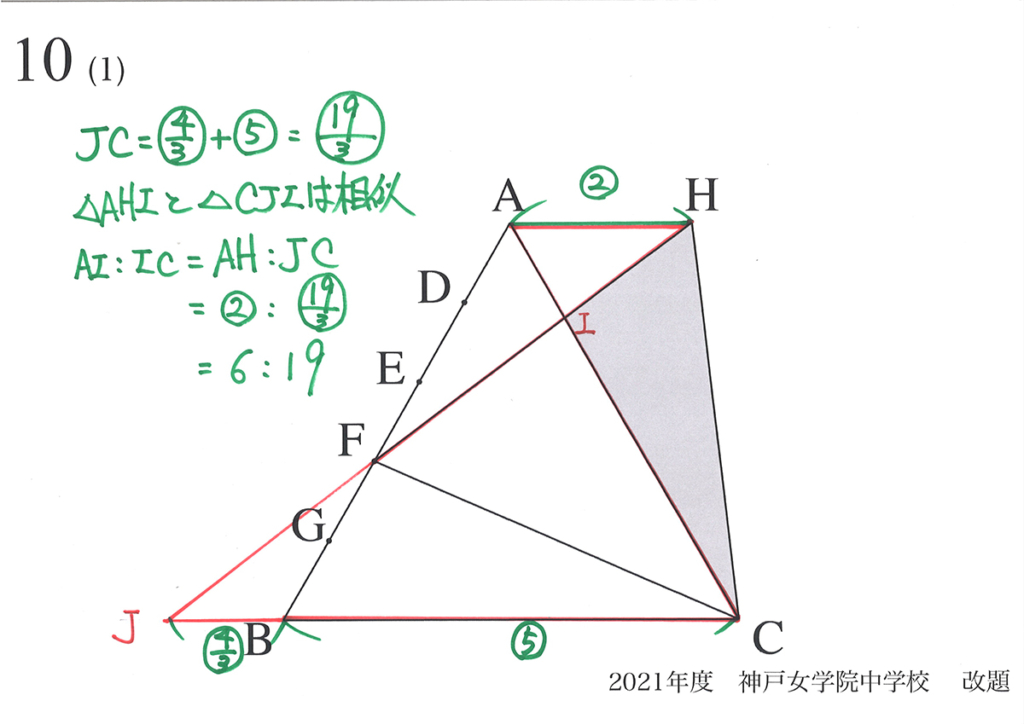

テストの点数ばかりを追いかける「利発な賢さ」よりも「のびのびした賢さ」へ。
もちろん「テストの点数も大事」ですが、「点数ばかり追いかける姿勢」は考えものです。
大抵の事はネットの検索で「知識としてはわかる」時代になってから、大分時間が経ちます。
「自ら考えてみる」姿勢は、学問への基本的姿勢として最も大事です。
そうした姿勢から、子ども自身が、



僕は、
算数が好き!



私は、
地理が好き!
このように好きな科目が出来ると良いでしょう。
「将来どういう人になりたいか」を、ほんの少し考えてみて、



僕は、
〜になりたいかな・・・



私は、
〜になりたいかな・・・
未来を色々と想像して、いろいろ考えてみることも良いことです。
「〜になりたい」は生きてゆくプロセスで、色々変わってゆくこともあります。
興味が出てきたら、自分が「読みたいから」本を読む姿勢が身につくと、とても良いです。
こうして「のびのびした賢さで学ぶ力を発展」する姿勢は、学びの根本的姿勢として大変良いです。
こういう姿勢を持つことは、受験においても「内なるパワー」を生み出すでしょう。
中学受験・高校受験・大学受験などに向けても、子どもにとって非常に大きな力になると考えます。
次回は下記リンクです。



