前回は「模試の結果・模試への大事な姿勢〜小学校での受験生・序列付けと同級生・「点数・偏差値のレッテル」と序列化・模試の判定と不安な気持ち・模試の結果・判定・模試を活かす気持ち〜」の話でした。
気になる模試の判定:合不合判定テストの結果

今も評判が良いと思われる四谷大塚の「合不合判定テスト」。
筆者が受験生だった1990年頃は、
 塾講師
塾講師受験校がどこであろうと、
合不合判定テストは受けるべき!
「受験生ならば、合不合判定テストは受けるべき」という雰囲気でした。
そのため、大勢の受験生が受けることになります。
すると、まさに「合不合判定」の精度が高くなってゆきます。



僕は〜点
だった!



僕は〜点だから、
勝ったぜ〜!



すごいっ!
じゃあ、算数は何点?



え〜と・・・
算数は120点だったな・・・



俺は135点だから、
算数は勝ったな!
筆者が通っていた塾では、合不合判定テストの結果を大勢の同級生たちが言い合っていました。
その中、



やあ、みんな!
合不合判定テストはどうだったかな?



440点
超えた人はいるかな?
「440点超えた人は?」と問う先生に対して、



はい。
超えました。
ただ一人「手を挙げていた」Iくん。



それはすごいな。
何点だった?



はい。
僕は458点です。
合不合判定テストで、合計450点以上を獲得したIくん。
本当にすごいです。(458点は筆者の記憶)


通っていた学習指導会の武蔵を目指すクラス「武蔵特訓」。
このクラスでは、非常に優秀な人物が集まってました。
皆「合不合判定テスト」では、かなり良い点数を獲得していました。
その中、筆者は「励みになる」というよりも、



みんなとても
高い点数を取っている・・・



このままでは、
まずい!



なんとか
しなければ・・・
「なんとかしなければ」という気持ちで一杯でした。
みんな良い点数とってますが、I君の点数は文字通り「別格」でした。
テストや問題では、「選択式」と「記述式」に大きく分かれます。
人によって、「どちらかが得意で、どちらかが不得意」と傾向が出ることもあります。
あるレベルの学力を超えると、「選択でも記述でも、どちらでも問題なし」となります。
問題の形式がどうであろうと、解答へ至る能力があるのです。
そういう子は少数ですが、必ず毎年何人かはいらっしゃいます。
Aくんを見て、誰しも思いました。



彼ならどの中学校を受けても、合格するな・・・
しかもトップ層で・・・
「必ず合格する」レベルにいたIくん。
抜群の成績だったにも関わらず、別に偉ぶるわけでも、騒ぐわけでもないIくん。
むしろ、淡々としていたのが印象的でした。
受験生の立場になると、「点数で序列化される」気持ちになります。



Iくん、すごいというか
どうやって、あの点数を・・・
「序列が遥かに下」であった小学生の頃の筆者は、Iくんを仰ぎ見るような感じで、



少しでも、
追いつきたい・・・
「追いつきたい」と思いながらも、心の奥底では、



まあ
無理だけど・・・
「無理」と思っていました。
とにかく、自分も頑張って成績を上げるしかありません。



とにかく、
しっかり復習しよう・・・
そこで、模試で出来なかった問題は「しっかり出来るように」復習しました。
合格判定と試験結果:一喜一憂しすぎない姿勢


やがて、受験当日を迎え、学習指導会のクラスメートのほぼ全員が同じ第一志望校を受けました。
そして、合格発表となりました。
筆者は運良く合格しました。



本当に良かった・・・
合格できた・・・
そして、Iくんは・・・・・
なんと不合格だったのでした。
合格して浮かれていた筆者は、その話を聞いてビックリ仰天しました。



えっ・・・
なんで?!



あの点数をとった
Iくんが?
まだ小学生だった筆者にとって、「この時ほど驚いた」ことは稀だったほどでした。
そして、少し時は流れ、東京の中学受験が終わって2月中旬頃になりました。
風の噂で、Iくんが「第二志望の学校に行くことにした」を、この頃に聞きました。



こんなことも
あるんだ・・・
こんなことも、現実には「起こりうる」のです。
「試験は水物」と言われます。
オリンピックでも何でも競争することには、必ず「番狂わせ」な事態も生じます。
ある方は、



人生には、上り坂も
あれば下り坂もある・・・



ところが、下り坂どころではない
「とんでもない坂」が起こりうる・・・



それは・・・・・
「まさか」だよ!
このように言いましたが、「まさか」が中学受験〜大学受験でも、必ず起きます。
筆者自身の中学受験の頃の体験を書いていて、ふとIくんのことを思い出しました。
フラッシュバックのように30年の長い時を経て、



Iくんって、
いたな・・・
Iくんを思い出して、この記事を書きました。
Iくんとは塾で同じクラスだっただけで、大して話したこともなく「それっきり」でした。



Iくん、今は
どうしているのだろう?
Iくんの名前を検索してみました。



・・・・・
あっ、いた・・・
Iくんらしい経歴で、しっかりと仕事をしていることが分かりました。
懐かしかったのと、なんだか嬉しくなって、



そういえば、
こんな顔だったな・・・
画面見ながら、思わずニコリと微笑んでしまいました。
大人になれば分かりますが、顔つきは小学生の頃と「大して変わらない」ことが多いです。
筆者は彼のことをハッキリ覚えていますが、彼は筆者を覚えていないかもしれません。
でも、昔の友達を見つけた気分で、嬉しくなりました。
合格判定は「一つの指標」:本番に活かす姿勢


この話は、実話を元に書いています。
もう「とうの昔に忘れ去っていたこと」を、この新教育紀行を書いていて思い出しました。
一つ、誤解がないように大事なことです。
この話は、現在の成績優秀者が「将来に不合格になる可能性」を示唆しているのではありません。
逆に「模試の成績からして、合格するはずのないと思われる学力の子が合格する」も一定数起こります。
人生では様々な「まさか」が起きますが、それは中学受験業界でも起こるです。
「合不合判定テスト」でもなんでも、模試の判定は、「一つの指標」に過ぎないのです。
その結果に、左右され過ぎることはないです。
「合不合判定テスト」は、画一的な問題形式・採点方法となります。
画一的なことが悪いことではなく、これはどうしても仕方のない事です。(上記リンク)
様々なカラーのある学校に対する判定を「同一の試験によって一斉に判定を行う」テストです。
そのため、「画一的」で「平均的」なことが「合不合判定テスト」に望まれていることでしょう。
読者の方には、ぜひ第一志望校に合格して欲しいです。
そして、それに向かって邁進して欲しいと思います。
「結果に振り回されすぎる」必要はありませんが、試験に対して「全力を出す」ことは最重要です。
・「模試を活かす気持ち」を持つ
・「本試験の予行練習・トレーニング」と言う姿勢を持つ
・大事なことは「模試の成績をあげる」ではなく、「本番で合格する」こと
模試を受けて、点数・偏差値・順位がつけられる受験生たち。
大人は仕事で色々苦労しますが、この「点数・偏差値・順位がつけられる」のは、かなり苦痛でしょう。



今回は偏差値59で、
第一志望校の判定はBか・・・



私は偏差値61で、
第一志望校の判定はギリギリAだった・・・
社会人の方で、「仕事で嫌なこと」があるかもしれません。
もし、その「嫌なこと」と「点数・偏差値・順位がつけられる」ことの「どちらかを選ぶ」時。



やっぱり
順位とかつけられるのは、ちょっと・・・
多く社会人は、前者を選ぶのではないでしょうか。
その中、必死に歯をくいしばって勉強を続けるのが、
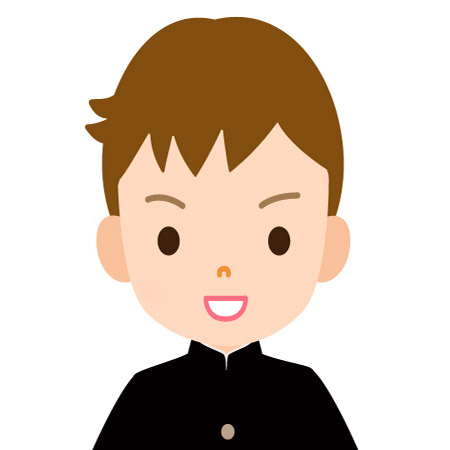
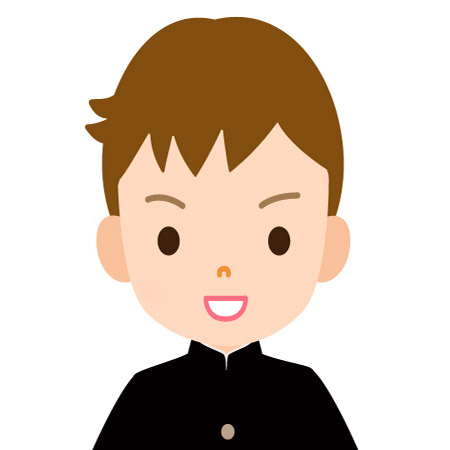

今度こそ、
第一志望校でA判定出したい!



偏差値下がっちゃったから、
もっと頑張ろう!
中学受験生・高校受験生・大学受験生たちです。
模試は「一つの結果」であり「本番に活かすのが大事」で、しっかりと模試を活かしましょう。
本人が「全力を出し切る」ように日々勉強することがベストでしょう。
次回は下記リンクです。



