前回は「記述の良い書き方と勉強法〜キーワードを軸に展開・「自分の意見を述べる」こと:求められている「答え」と意見・子どもが「書く文章」にバツをつけない姿勢〜」の話でした。
算数・理科の記述のコツと勉強法:思考の流れを表現
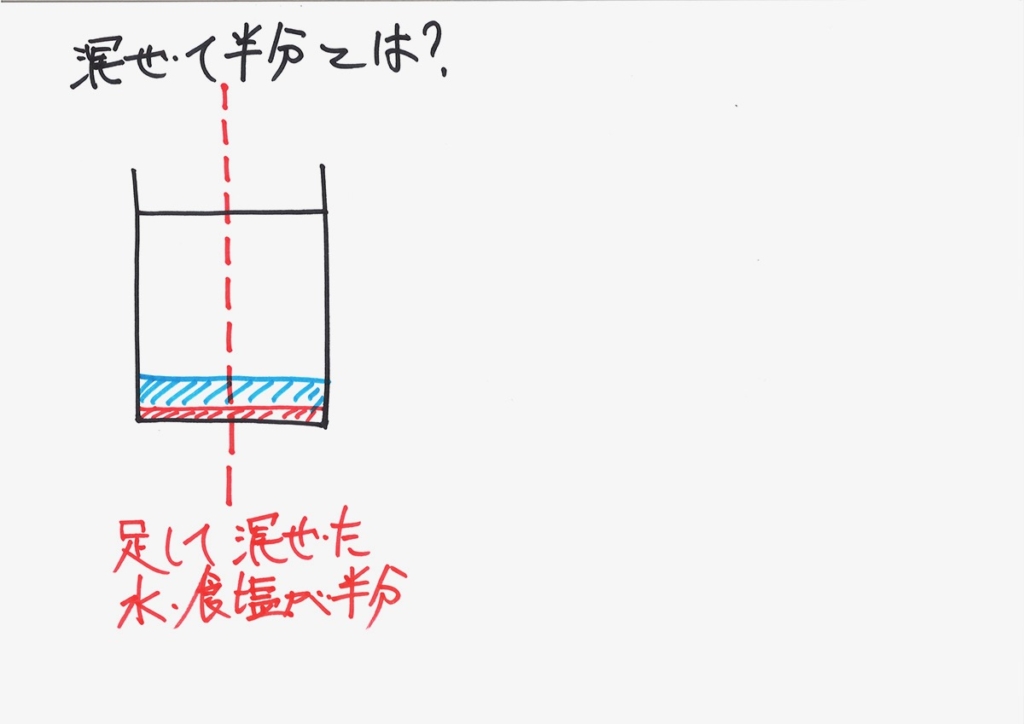
算数や理科で「想定される答え」がある記述式問題は、まずは「答えが分かる」ことが大事です。
答えが分からなければ「記述しようがない」のも事実です。
 男子小学生
男子小学生そうなんだよね・・・
だから、結局「解けるようになる」ことが先なのかな・・・
記述式の算数・理科は、社会よりも「答えの方向性や軸」が明確である傾向があります。
上のてんびん算の問題では「混ぜて半分」が最も大事なポイントです。
上のような食塩水を混ぜる絵を描いて、「思考の流れを表現」すると良いでしょう。
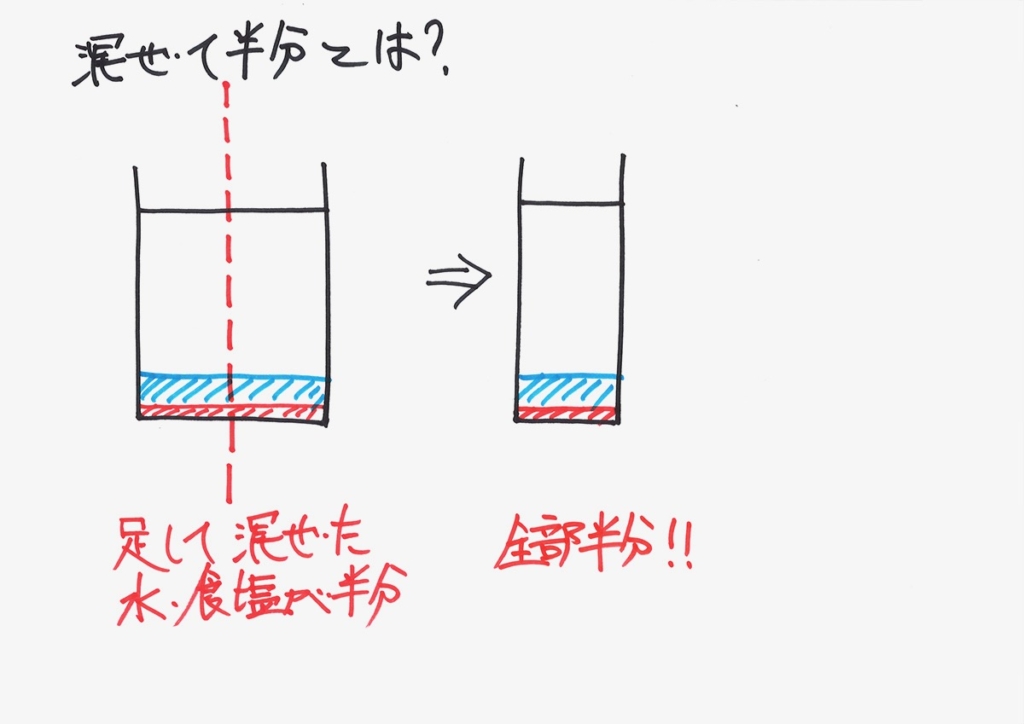

記述の算数は「誤っていても解答に辿り着いている」ことが望ましいと感じる方もいるかもしれません。
上記のように「食塩水を混ぜる」ことを図解して考えることは、大事な理科的思考です。
途中で終わっていても、



時間切れで、
ここまでかな・・・



大事な方向性が
分かっているから、3点ほど上げよう・・・
このように「ある程度の点数」を与えるでしょう。
上の例では「混ぜて半分とは?」と「説明のために記載」しています。
これを「答案に書く」ことの是非はあるかもしれませんが、筆者は「良い」と思います。



答案ではなく、
メモ書きに過ぎない。
このような意見もあるかもしれませんが、「何を考えているのか」が明確なことは良いことです。
記述式は「分かること・理解していること」は途中まででも良いので、ハッキリ書いてゆきましょう。
・図や絵を描いて「考えていること」を表現
・思考の流れをメモなどで書くことは、記述力だけでなく学力アップにつながる
メモ書きでも走り書きでも書く:採点者が考えていること


記述式の多い学校の教員・採点者は、



この子は、どのように考えて
いるのだろう?
このようなことを考えながら試験の採点するのでしょう。
記述式の採点において、



何を考えていて、
どこまで理解しているか?
採点者は「理解の程度」を答案から一生懸命読み取って、点数をつけます。
途中で終わっても、端的でもメモ書きでも良いから「とにかく表現する」ことが大事です。
「分かっていても」書いていないと「読み取りようがない」のです。
白紙、あるいは白紙に類ずる答案では採点者は、



これは
✖️にせざるを得ない・・・
点数のつけようがないのです。
書いている途中に、



あと一分で
終わりです!
「まもなく試験が終了」になってしまうケースもあるかもしれません。
その場合でも、走り書きでも良いので、



僕は、
ここまでは分かっているよ!



私は、
ここのあたりは分かってます!
このように「とにかく分かっていることを表現する」ことがベストです。
「書くこと」に慣れる姿勢


そのためには、「書くこと」を好きになって欲しいです。
塾のテキストや模試などで「記述式」問題の答案を書いた結果、



あ〜あ、
✖️だった・・・



私は、
半分の点だった・・・
そういう時、がっくりしないようにしましょう。
大事なことは、試験当日に出来ることです。
その前に「出来るか、出来ないか」は大きな問題ではないのです。
記述は難しくないので、書くことに慣れるために「日ごろ書いてみる」と良いでしょう。
例えば、小学生新聞など読んで、まとめたり、自分の感想を書くと良いでしょう。



この記事は、
僕は〜と思ったけど・・・



私は、〜が
大事なことだと思う・・・
そして、親は子どが自由に意見などを書いてみたことに、



この辺は
いいんじゃない!
親は暖かめに◎や○をつけてあげましょう。



これは記事の内容と
ちょっと合わないかな・・・
「ちょっとズレている」場合でも✖️にはせず、



これは△かな・・・
もう一度読んでみて!
△をつけてあげましょう。
そして、塾などで✖️をもらってきたら、



ちょっと違うみたいだけど、
一生懸命書いたじゃない。



もう少し、
このポイントを書けるようになるといいね!
「書いたこと」を褒めてあげましょう。



模範解答や
考え方を学んでみたら良いよ!



ママと一緒に
読んだみようか。



うん。
ちょっと分からないから、一緒にやって!
子どもと一緒に、子どもの書いた答案と模範解答を一緒に読んでみましょう。
・問題文の文章内のキーワードを拾い出す
・キーワードを軸に文章で表現されている内容を「自分なりに理解」して展開する
そして、少しずつ「書くこと」に慣れてきて、



自分の考えていることを書くのは、
楽しいかも。
ポジティブな気持ちになると良いでしょう。
そういう気持ちになると、記述式問題が得点源になるでしょう。
次回は下記リンクです。



