前回は「合格へ向かう姿勢〜「志望校に登校すること」をイメージ ・志望校のカラー・雰囲気を実際に感じる・学校の中に入ってみる〜」の話でした。
本番で実力を発揮する姿勢

受験では「本番で実力を発揮すること」が最も大事です。
受験当日に、「ここまでは出来ている」と考えることの大事さの話です。
「良い面に目を向けること」は実社会でも大事なことです。
「ここまでは出来ている」と自己肯定することは、試験においても「大いなる安心感」に繋がります。
試験で最も避けたいこと。
それは
 男子小学生
男子小学生あ・・・
分からない・・・



困った・・・
全然出来ないから、気持ちが焦ってしまって・・・
「焦ったり」「慌ててしまい」ミスを繰り返すなどで、「実力が発揮されないこと」です。
持っている力を出し切る姿勢


例えば、本人が「100という学力(一つの例えです)を持っている」と仮定します。
試験当日、奮起して105とか110くらいの力を出してくれるとベストでしょう。
まずは、



持っている100の力を
出し切る!
自分が持っている力をしっかり出すことが、最優先です。
「100の力を出し切った」結果、試験のラインが120で不合格となってしまうとき。
それは、一面致し方のないことです。
一方、試験のラインが95に対し、



100の力を持っていたのに、
出しきれずに90だった・・・
その結果、不合格となること。
これは「絶対に避けたい事態」です。
算数においては、難関校は大抵4問程度の大問に別れていています。
さらに、小問に別れていることが多いです。
出題者としては、大問の最も本質的なところを、



これが解けるか、
ズバッと問いたい・・・
こう考える出題者もいるでしょう。
ここで、



ちょっと難しすぎる
かな・・・



解ける人が少なくて、
点差が開かないかも知れないな・・・
こう考える時、問題をアレンジします。



ある程度の点差がつかないと、
出題の意味が薄れてしまう・・・



小問に分けて、学力によって点差がつく
ようにしようか・・・
小問に分けるなどして、問題を作成します。
「大問が小問に分かれている」とき、その理由の多くは下記です。
1.小問が「考えるヒント」となる。
2.問題と点数を分割することで、学力差が適切に反映される
「自分が持っている力を出し切る姿勢」は、日頃の勉強姿勢が大事です。
「一つ一つしっかりと理解」してゆく考え方が良いでしょう。
自己肯定感とポジティブな考え方:「ここまでは出来ている」と思う
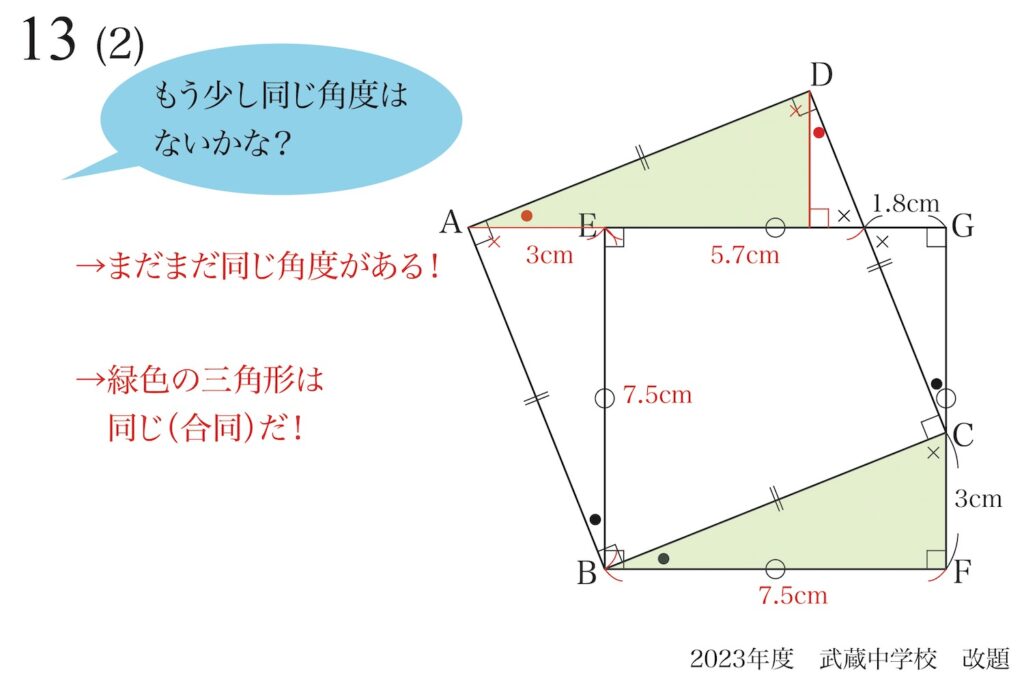

大問に4つの小問があるとして、(1)(2)まで解けたとします。
そこで、(3)は上手く解けない場合、



もう少し粘って
もうちょっと考えよう!
あるいは、



ちょっと、つまづいている感じだから、
他の問題に移ろう!
このように「他に行こう」と考えることもあります。
いずれが良いかは、ケースバイケースです。
ケースバイケースですが、「とても大事な考え方」があります。
それは、



(2)までは、
きちんと解くことが出来た!
まずは、「出来た」ことに対して自己肯定することです。
そして、



ここまでは出来ているから、
ある程度は点数が見込める!



他の問題も、
この調子で解けるはず!
こう思うことは、とても大事なことです。
その時に、自主的に



よし!
もう少し頑張ろう!
こう考えることがベストです。
まずは、



ここまでは
出来ている!
安心感を強く持って、続けて試験に臨むのが良いでしょう。
「出来ないところ」ばかりではなく、「出来ているところ」に目を向けるのが良いでしょう。
ポジティブな気持ちで入試当日まで、志望校をイメージし続けると良いでしょう。
そして、「直前期からは全力で駆け抜ける」のが良いでしょう。



あなたの偏差値は
58です。



あなたの偏差値は
52です。
受験生である間は、とにかく点数・偏差値という「数字のレッテル」が貼られ続ける受験生。
さらに、



あなたのA中学の合格可能性は
60~80%程度です。
合格判定や合格可能性が、ハッキリと提示されるのが受験生です。



「60~80%程度は合格」なら、
「20~40%は不合格」ってこと?
合格判定が出されて、



僕、本当に
A中学に合格できるのかな?
不安が続き、苦労が絶えないのが受験生です。
受験勉強は「自分が行きたい中学校・高校・大学」へ入るためのプロセスです。



A中学に合格した
後は、色々なところに行きたいな!



B中学に通って、
英語をしっかり勉強して、海外に行きたい!
「合格後の楽しい人生」を想像して、当日までポジティブな気持ちで乗り切っていきましょう。
次回は下記リンクです。


