前回は「諸藩のカラーに大きな影響を与えた藩祖の存在〜藩祖「伊達政宗」の巨大な影響・私立中高一貫校のカラーと日本の大学・「別格」の仙台藩と薩摩藩〜」の話でした。

仙台藩と会津藩:新政府軍と松平容保

当時、62万石と諸大名の中では加賀100万石、薩摩77万石に次ぐ大身の大名だった仙台藩。
さらに、伊達政宗という別格に優れた超有名人を藩祖に持っていた仙台藩。
それだけに、伊達政宗を藩祖とする仙台藩は、高い意識を持っていたに違いないでしょう。
 仙台藩士A
仙台藩士A俺たち
仙台藩士は他の藩士とはちがう!
ところが、その名家・名藩であった仙台藩は、幕末に大きな岐路を迎えます。


最有力の佐幕藩であった会津藩松平家がすぐ隣にいる環境の中、会津藩と新政府の間の折衝役を務めます。



我が兄を
支えているのだが・・・



情勢は
幕軍に著しく不利だ・・・
当時32万石を誇り、徳川一門であった会津藩と新政府の間を取りなす役となった理由。
それは、名家・名藩ゆえでした。



仙台藩ならば、
この状況をまとめられるだろう・・・
他の藩では「荷が重すぎる」事態でした。
そして、仙台藩の首脳が佐幕だったことも、大きく影響しました。
この頃、10歳くらいだった後藤新平。



仙台藩は
どうなるのだろうか・・・
現代であれば小学校4~5年生で、物心ついて分別もあります。
強気の後藤少年と言えども、



僕たちは
大丈夫なのかな・・・
不安な日々を送っていました。
会津松平藩:徳川家康の元の名前「松平」


32万石の会津藩は、「松平」という「徳川家康の元の名前(姓)」を冠する大名でした。
そのため、会津藩もまた「別格」の大名でした。
元々は、三河を支配していた松平家に生まれた家康。



私は、松平家に
生まれたのです!
しかし、相次ぐ戦乱の中、松平家は急速に衰退します。
そして、東側の大勢力で駿河・遠江を支配する今川家に事実上吸収されました。


徳川家康は、桶狭間の合戦で今川義元が織田信長と戦った際、「今川軍の一員」でした。
「一員」というよりも、「今川軍の先陣」として、織田軍と戦っていたのです。
その時の名前は、「松平元康」です。



私は、
松平元康だ!
「元康」の元の字は、今川義元から一字を拝領した名前でした。
「一字を拝領する」ことは「重んじられている」証拠ですが、当時、松平家は今川家に従属していました。
「重んじられている」とは言え、今川家の「家臣のような存在」だった松平元康。
桶狭間の戦いでは、今川家よりはるかに勢力が弱かった織田信長が、奇襲攻撃で今川義元を討ち取ります。


桶狭間の戦いの後、弔い合戦もしない後継者の息子・今川氏真と断交します。
そして、織田信長と同盟を結びます。



今川とは、
縁を切った!



その証に、
「元康」の名前は改めなければ!
そして、「独立大名として新たな人生」を切り拓くにあたり、名前を変えたのです。



今日から、
私の名前は徳川家康だ!
そして、松平元康から徳川家康へなったのでした。
幕末のうねりに飲み込まれてゆく仙台藩


とは言え、徳川幕府にとって神君・家康の旧姓であり、そもそもの実家である「松平」。
徳川幕府は、徳川家光の時代に異母弟・保科正之を「松平姓」に改めさせ、会津を任せます。



我が弟、
正之よ・・・



徳川家出身のお前だが、
この際「松平」になってもらいたい・・・





分かり申した!
お任せを!
そして、徳川御三家に準じる家格として、威風を放った会津藩。
この「松平」を冠する特別な会津藩。
会津藩と新政府軍の間に入る立場の藩は、「伊達・仙台藩しかいない」のでした。



会津藩は
全面降伏しろ!
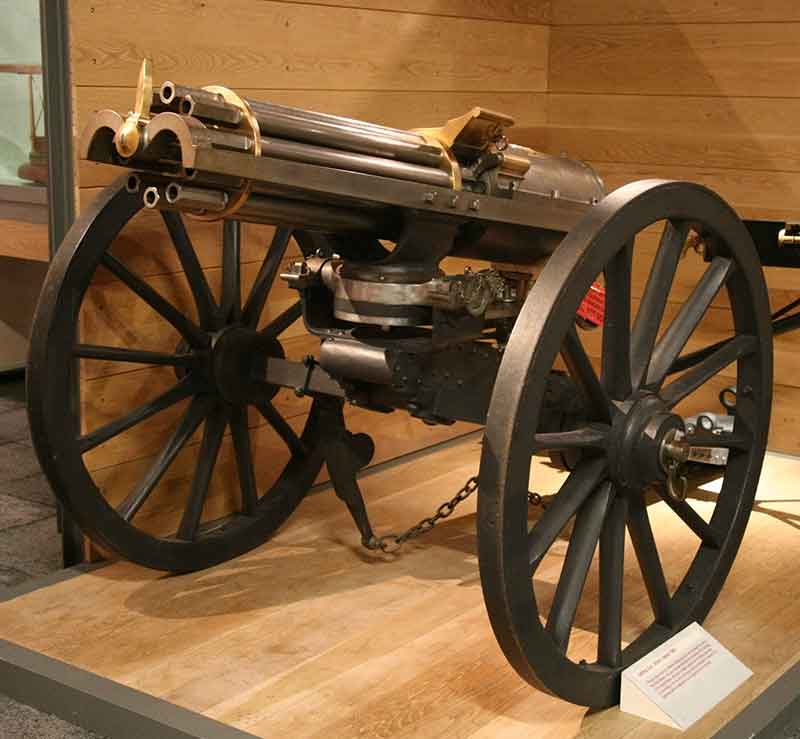
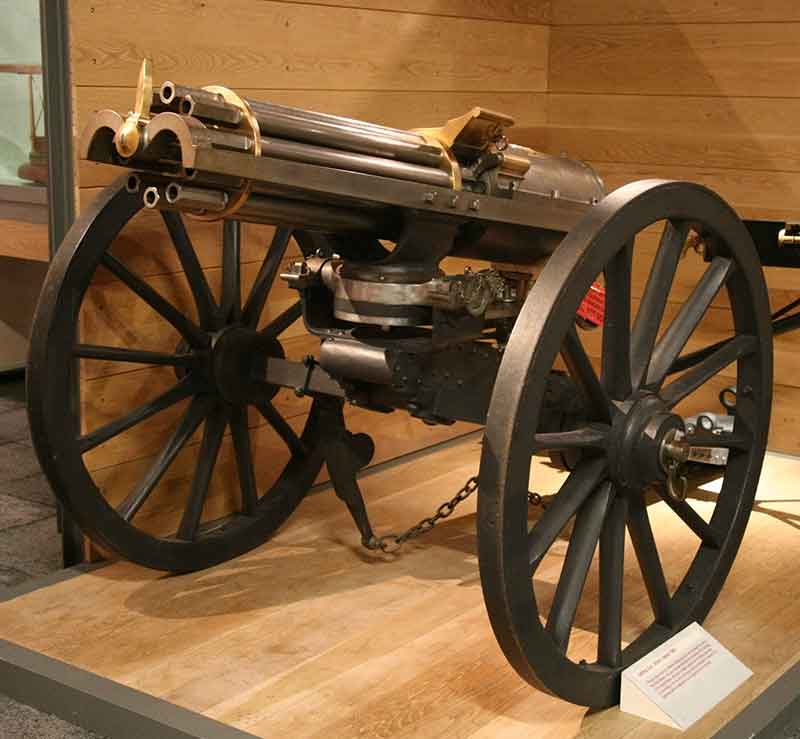

そのような
一方的な要求は呑めない!
しかし、その交渉は決裂してしまいます。



戦うしか
ないのか・・・
当時、質実剛健な武士を産んでいた会津藩は天下に定評が非常に高い藩でした。



武士といえば、
西の会津か東の薩摩!
「西の会津か東の薩摩」と言われたほど、強力な藩であった会津藩。
そして、幕末期には大人しめだったものの、雄藩の一角を担っていた仙台藩。
幕末の猛烈な「時代のうねり」に、会津藩と共に巻き込まれてゆく仙台藩でした。
次回は上記リンクです。


