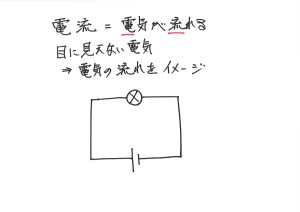前回は「かっ車の考え方・コツ・ポイント 4〜動かっ車の移動距離を描く・どこかの点に注目・大事なポイントに注目・理解して楽しく成績アップ〜」の話でした。
電気の基本:電圧と電流と抵抗
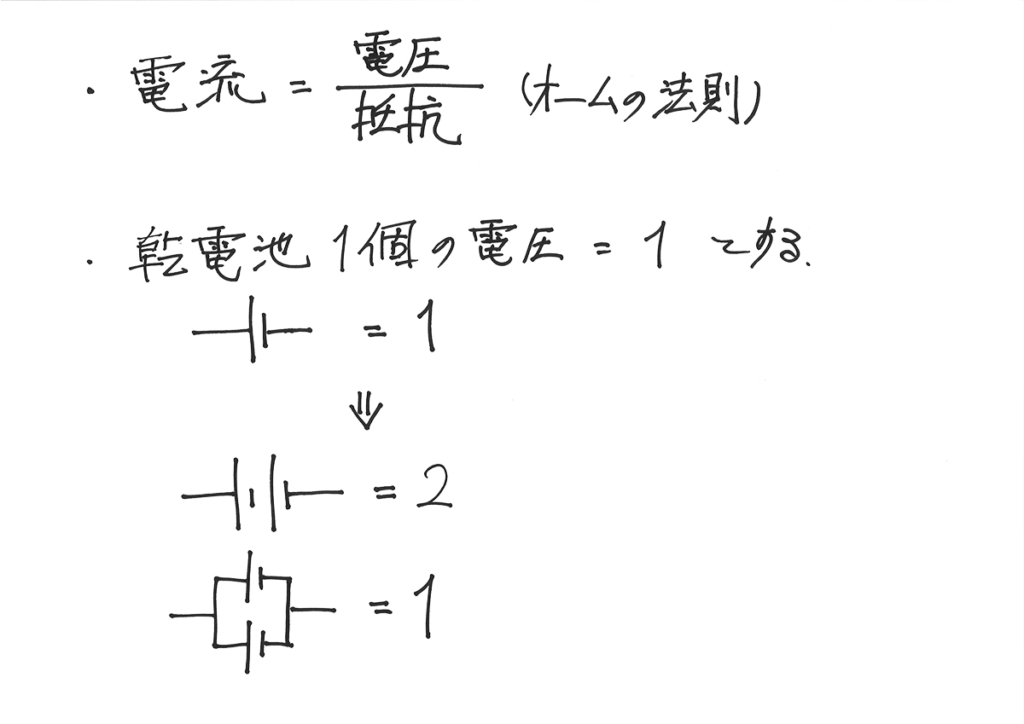
今回は、小学生・中学受験の理科の電気を考えてみましょう。
電気は電流・電圧・抵抗があり、オームの法則が基本です。
 男子小学生
男子小学生これは
知ってるよ。



この辺は
分かっているけど・・・



電池や電球が、沢山出てくると
わからなくなる・・・
「電流とは?」「電池とは?」と学ぶ時、上のような、物理法則が突然出てくることが多いです。
すると、



まずは、この公式(法則)を
暗記しなければ、ならないのね・・・



そして、公式(法則)をどう使って
問題を解くか、パターンを覚えなきゃ・・・
多くの受験生は、このように考えます。
それも良いのですが、「考えると楽しい」はずの理科が「暗記科目」になってしまいます。



だけど、公式(法則)は、
暗記しなければならないでしょ・・・
「公式は理解して暗記」が必要ですが、理科はイメージすることを大事にしましょう。
イメージがしっかり出来ていると、応用問題も解けるようになります。
電流とは?:流れる電流を描く
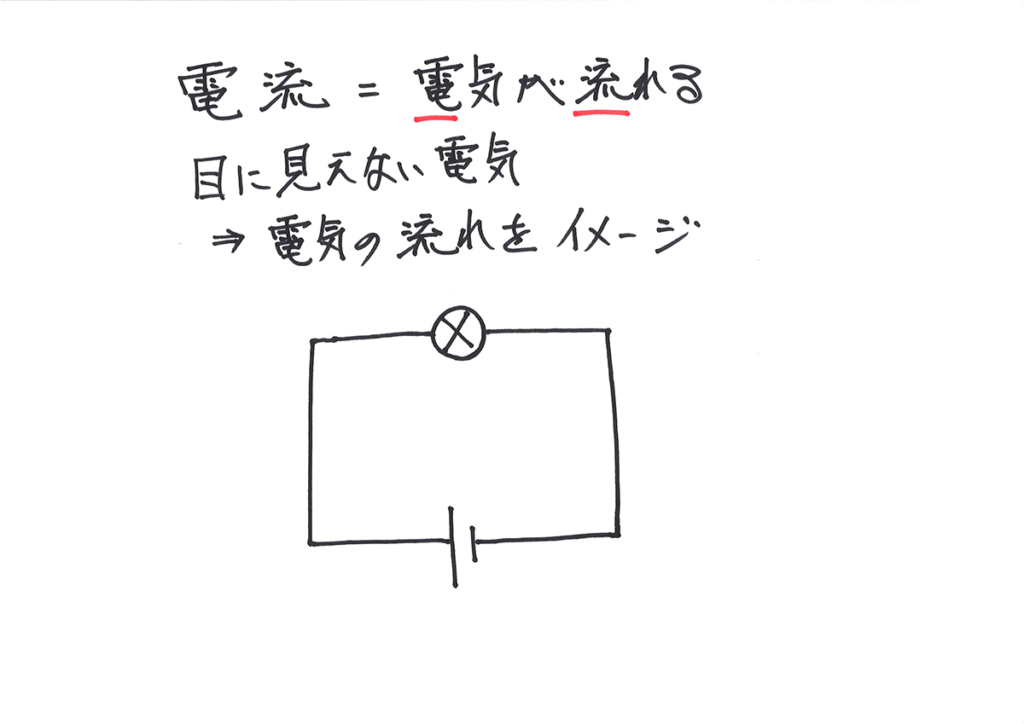

まずは、電流とは何か?を考えてみましょう。
基本回路の「電池1個と豆電球1個」を考えます。
「電流=電気が流れる」です。
電気は見えないですが、「流れている」のです。



確かに、電流って
「電気の流れ」だね・・・



でも、目に見えないから、
よく分からない・・・
この「見えない」ことが、電気が難しく感じる一つの理由です。
暗記ではなく、「考える」タイプの理科の問題を考えてみましょう。
電気・電流以外の、てこ・ばね・かっ車・ものの動き・実験などは、対象が見えます。
対して、電気・電流は「目には見えない」ので、



電気・電流は
どこにいるのか・・・



よく分からないから、
直列・並列とか暗記した方が早いかな・・・
ここで、電気が流れている様子を描いてみましょう。
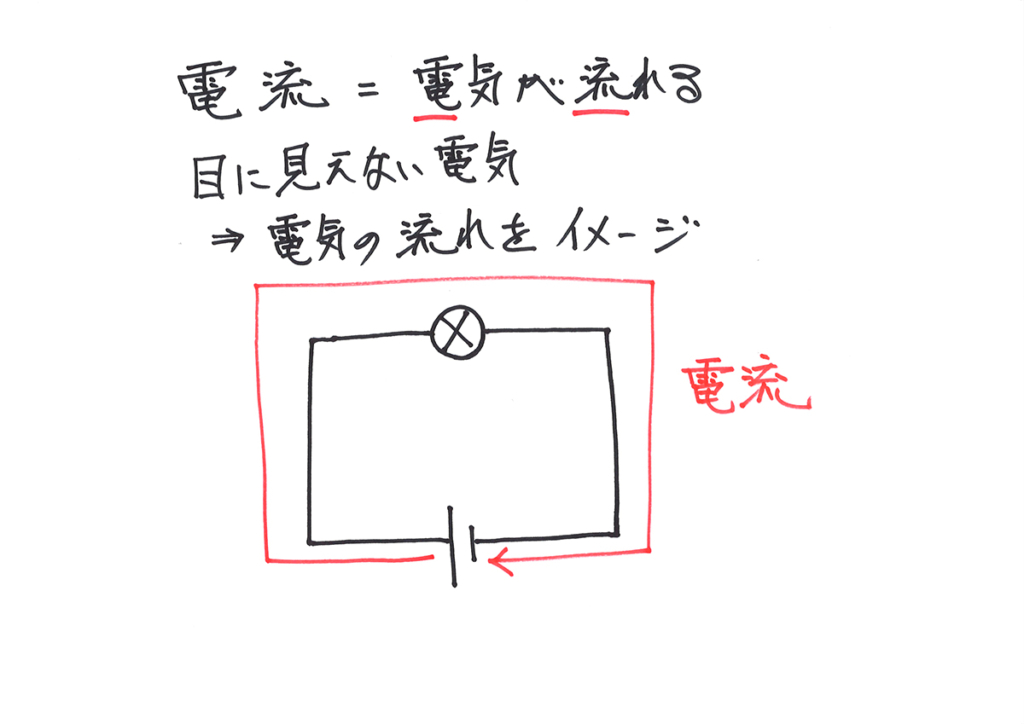

目には見えない電気・電流は、流れている状況をイメージして、電流を描くようにしましょう。
電流は「電池のプラスからマイナスに流れる」ので、上記のように描いてみましょう。



グルッと流れている
感じでいいの?
こうして、描いてみると「見えない」電気の流れがイメージ出来ます。
電池とは?:電流を「持ち上げる」役割
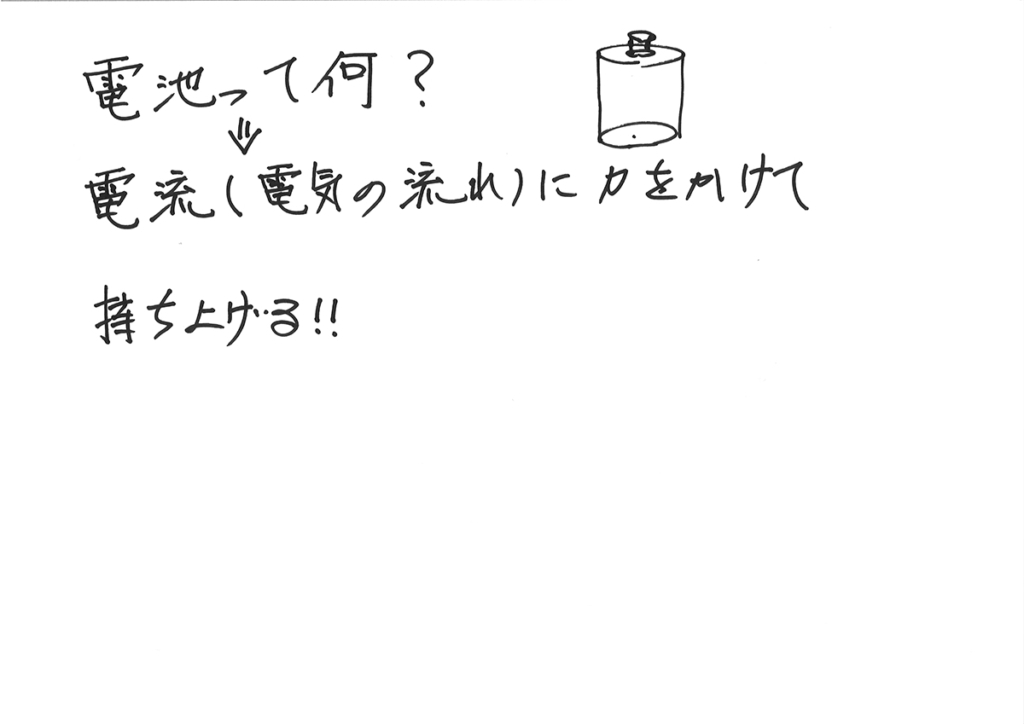

次に、「電池とは何か?」を考えてみましょう。
電池とは、「電流を流す」役目と「流れてきた電流を持ち上げる」役目を持ちます。
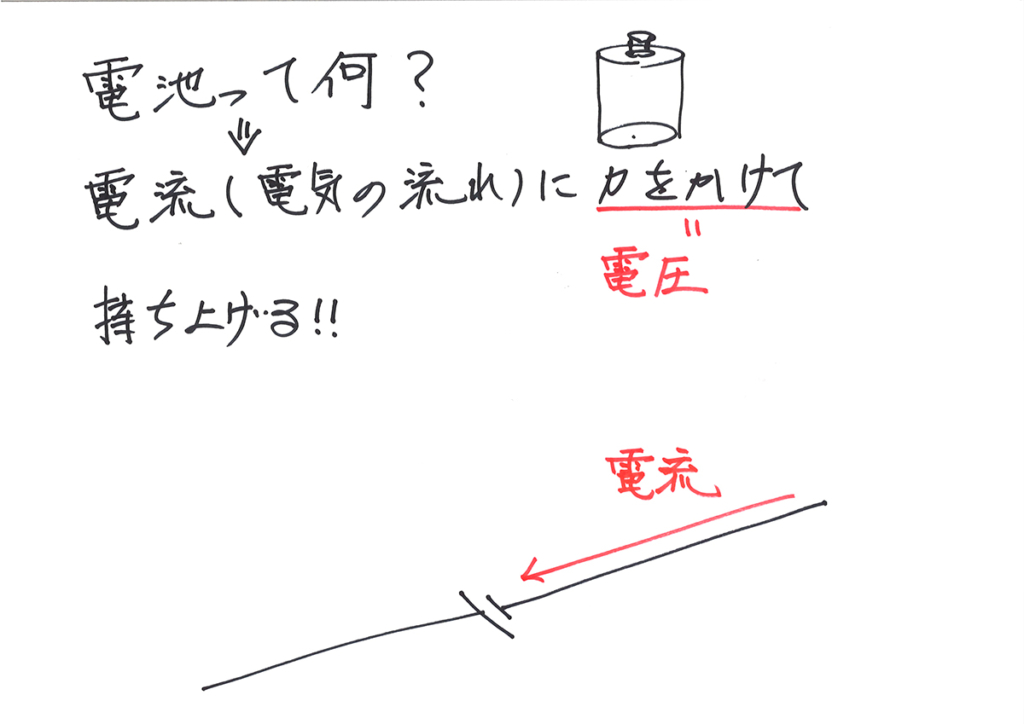

この「流れる電流を持ち上げる力・高さ」を「電圧」と呼んでいるのです。
これは、「電流がなかった時」も同じです。
電池が1個でも何個でも、「電流がない回路に電流を持ち上げて流れを発生させる」のが電池です。
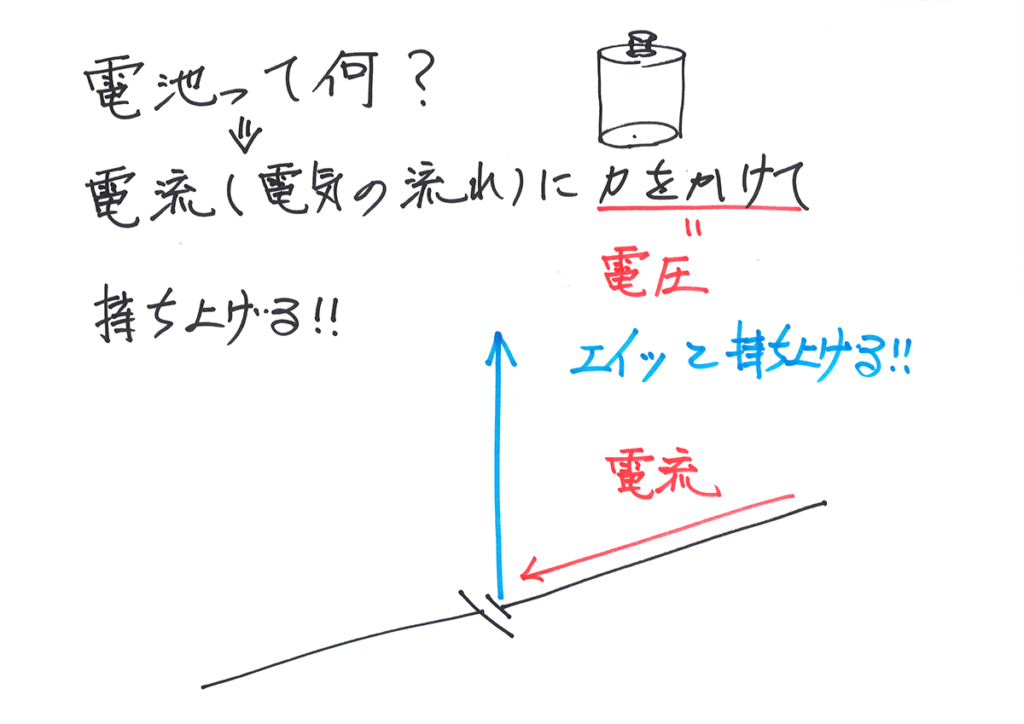

電流が流れてきて、電池のところにやってくると、電池が「エイッ」と電流を持ち上げます。
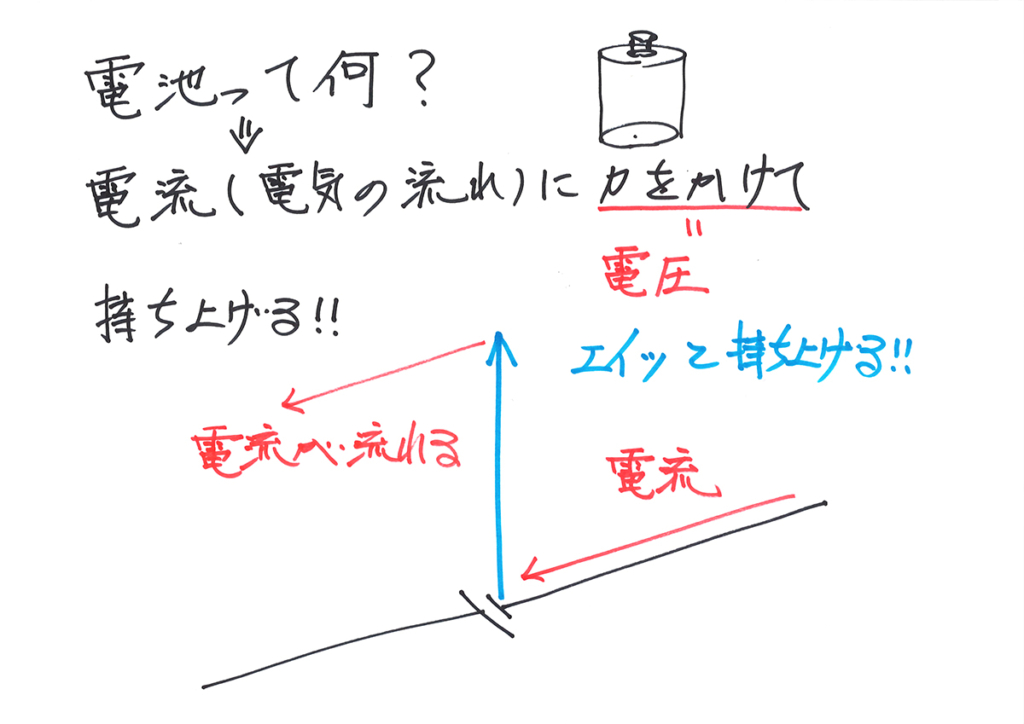

すると流れてきた電流は、「持ち上がったので、また流れることができる」のです。
つまり、「最初に流れてなかった電流を、電池がエイッと持ち上げる」役目をするのが電池です。
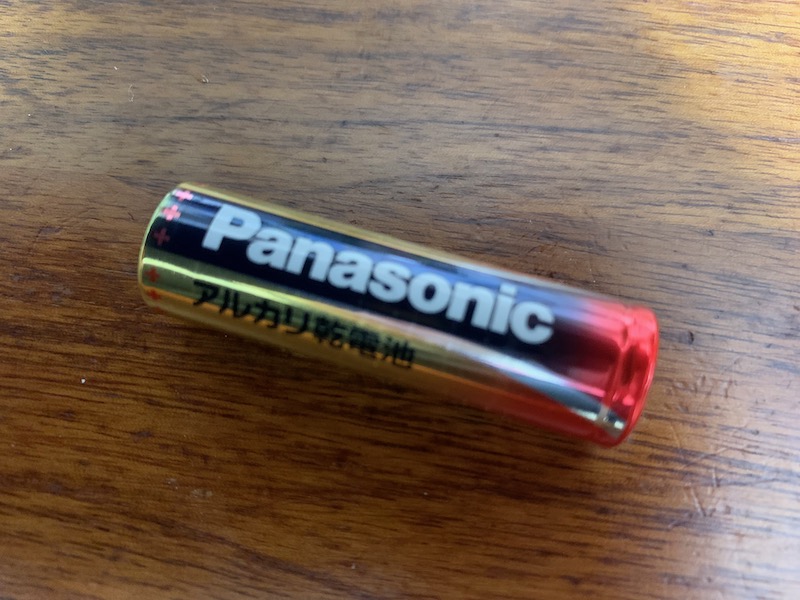
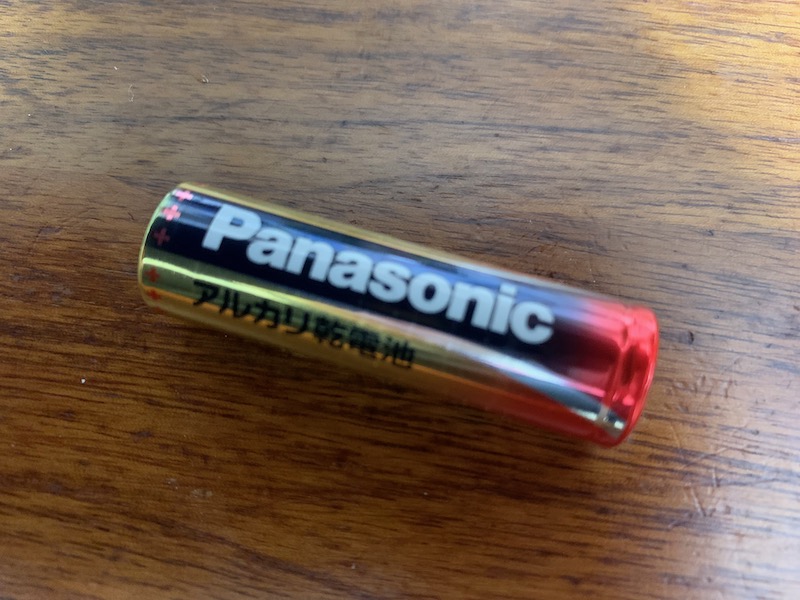

流れる電流を
持ち上げて、また流すよ!
電池は「持ち上げるパワー(エネルギー)」がある限り、
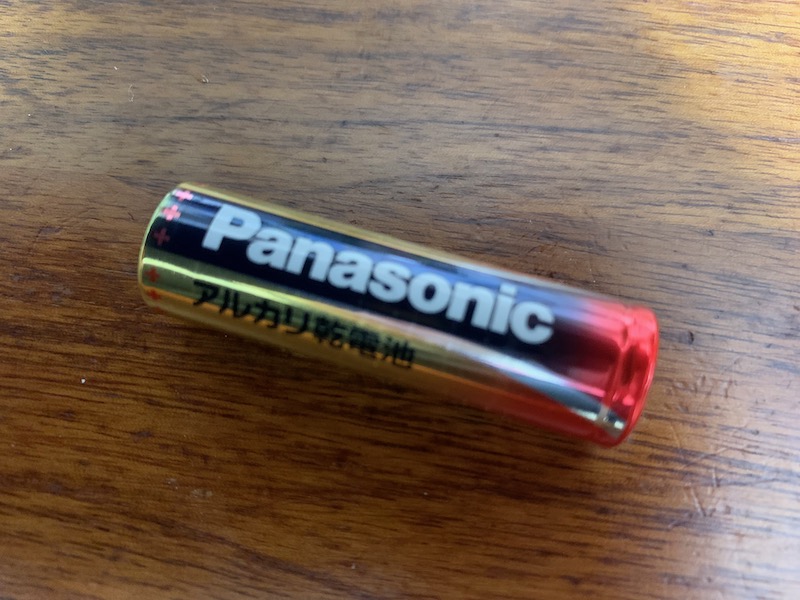
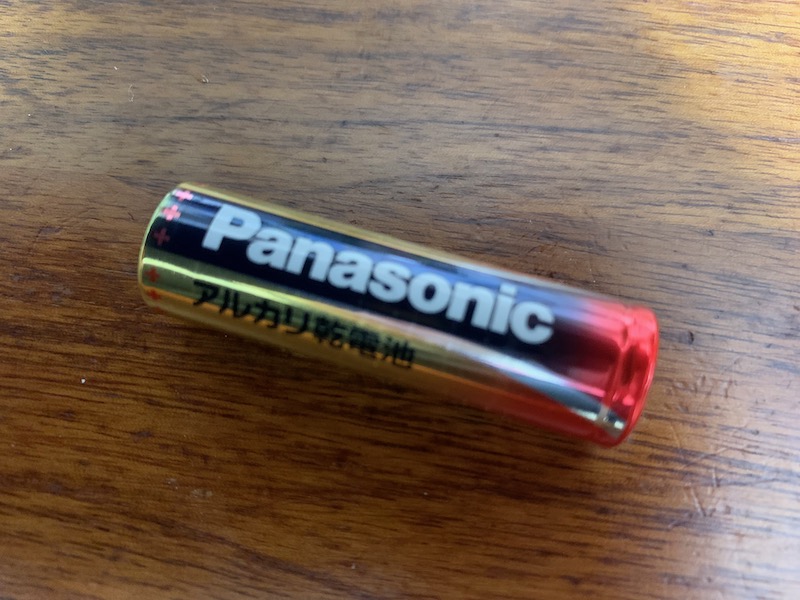

パワーがある限り、
何度でも電流を持ち上げるよ!
「流れた電流を何回も持ち上げる」ことが出来ます。
そして、「持ち上げる高さ=電圧」と呼びます。
例えば、単三乾電池や単四乾電池は「1.5V(ボルト)」の電圧があります。
・最初に電流をエイッと持ち上げて、電流を流す
・一周してきた電流を再度エイッと持ち上げて、電流を流す:持ち上げるエネルギーがある限り
この電気の流れ=電流を、「水の流れ=水流」で考えてみましょう。
電池が「エイッと持ち上げる」のは、何か似ているものがあります。



ポンプに
似ているね!
ポンプにとても似た役割をする電池。
電池がポンプのような役目を果たして、水を持ち上げて流します。
これを「水流モデル」と呼んで、参考書等で紹介されています。



なんで、電流なのに
水流って、水の話になるの?
それは、水流モデルは「モデル」であって、「こう考えると分かりやすい」考え方だからです。
上記の考え方は、水流モデルと同じことです。
かっ車・電気などの物理分野は、



この公式を覚えて、
次はこの公式・・・
このように「公式」ばかりではなく、これらの「基本的イメージ」を大事にしましょう。



なんとなく、公式ばかりだった
電流や電池が、少し分かった気がする・・・
最初は「なんとなく分かった気持ち」で良いでしょう。



電池が電流を持ち上げて、
流れるんだね・・・
最初は「大体」で良いので、そのイメージを大事にして、基本〜応用問題を考えてゆきましょう。
そして、電気の問題は、理科の問題の中でも比較的「パターン」に分けやすいです。
それらのパターンよりも、基本を理解して問題の考え方をしっかり理解しましょう。
次回は、電流・抵抗の基本の話をご紹介します。
次回は下記リンクです。