前回は「日本の中心から大きく離れた徳川家〜家康を「端=関東に追いやった」秀吉・関東平野の展望・河川・治水工事に悩む家康・武田と徳川〜」の話でした。
河川の氾濫に悩む信玄:山国甲斐の治水対策

「信玄堤」という堤防を築いたことで有名な武田信玄。
 武田信玄
武田信玄甲斐の国は、
山ばかりの国だ・・・



平地が少なく、
急な河川が多い・・・



そして、その急な河川が
氾濫を起こすのが多すぎる・・・



なんとか
しなければ・・・
元々は甲斐守護である名門武田家を次いだ信玄(晴信)は、父・信虎の代に甲斐を統一します。
信長や家康のように「城主とはいえ弱小勢力」とは異なり、「最初から一国の主」だった信玄。
信長の織田家は尾張守護でも何でもなく、まして「守護代ですらない」家柄でした。
信長の家は「尾張守護代の織田家」の「三人の家老の一人」の家柄だったのです。
つまり、守護・武田信玄にとっては、守護代ですらない信長は、格が二段ほど落ちます。





確かに
我が織田は、守護でも守護代でもない。



それが
どうした?



守護などという権威は
とうの昔に落ちているのだ!
守護・守護代と戦国大名:尾張と甲斐の比較


信長の父・信秀は、軍事的才能・政治的才能に非常に優れた人物でした。
信秀の代に、先進地域であった尾張において、津島湊(港)などをもつ地域を押さえて躍進します。
まずは、「経済力を確保」した信秀。
信長より13歳年上の信玄(晴信)。
「尾張の一部の領主」である信長と異なり「甲斐一国」を最初から持ちます。



私は
守護だ!
信長と異なり、「歴史的権威が好き」だった信玄。



私は、過去の権威を
大事にする!
それは、自分がもともと「過去の権威において上位者」の生まれであることも大きな要素でした。
元々守護・守護代だった大名=守護大名と、織田信秀・信長のように「実力での仕上がった」大名は違います。
後者を区別するために、「戦国大名」という名称が生まれました。
元々「守護大名」であった武田信玄は、「守護大名から戦国大名化した」ともいえます。
「尾張の一部」を領する信長と「甲斐一国全土」を治める信玄。
面積では、尾張と甲斐は同じくらいです。
はるかに信玄の方が「恵まれた立場」であるように思われますが、実態は異なりました。


上の図は秀吉の時代における太閤検地での各国の石高です。
「石高」というのは、お米の収穫量を示します。
よく、「百万石の加賀」と言ったりしますが、江戸時代も石高でお米の収穫量を示していました。
今はm(メートル)、g(グラム)、L(リットル)などで長さ・量を測ります。
昔は尺貫法と呼ばれる単位がありました。
一升:約1.8L(お酒の一升瓶など)
一斗:十升
一石:十斗(=百升=約180L)
この「石」がお米の量の基本であり、収穫量の基準となります。
お米の量はたくさんあった方が、たくさんの方が生活できるので、全ての基本となります。
秀吉の時代なので少し後ですが、甲斐は約22万石、尾張は約57万石です。
つまり、尾張のお米の収穫量は甲斐の約2.6倍になります。
この違いは非常に大きいです。
最初は「尾張の1/3ほどの領土しか持たなかった」信長。
お米の収穫量は「尾張の1/3が、甲斐全土より少し少ないくらい」です。
そして、尾張は京・山城に近く、甲斐よりもはるかに商工業が盛んな地域でした。


お米の収穫量と商業の先進性を考慮すると、だいたい「尾張の1/3」=「甲斐一国全土」になります。
商業が盛んな尾張は、大きな経済力がありました。
そのため、「尾張1/3」の方が「甲斐一国全土」よりも国としての力はあったかもしれません。
このように、甲斐守護だった信玄でしたが、それほど恵まれた立場ではありませんでした。
究極の治水術・信玄堤を思いついた徳川家康:武田信玄の遺産
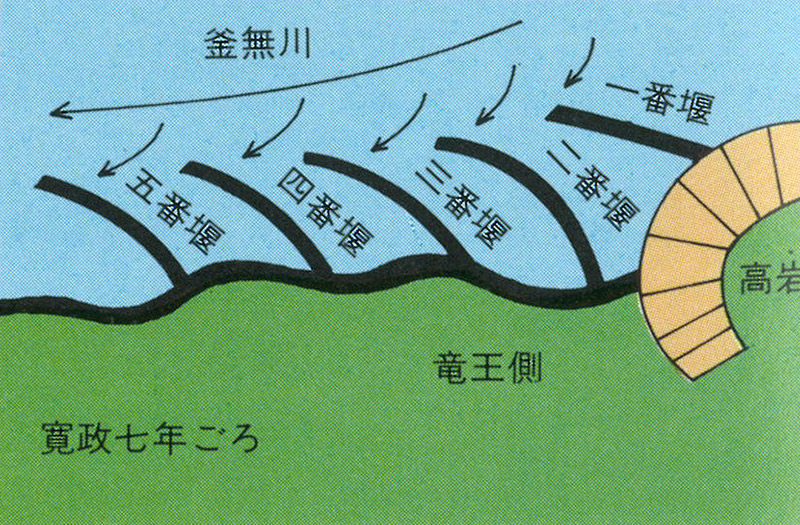




氾濫する
河川に堤防を築く!



そして、住民が過ごしやすい
国を作るのだ!



河川をしっかり整備すれば、
お米の収穫量も上がる!
そう心に決めた信玄。
長い時間と莫大な費用をかけて、河川に堤防を築き、釜無川などの川の治水に大きな成果を挙げます。



時間も費用も
かかったが・・・



これで、甲斐の国の
力はさらに強くなったぞ!
そして、長年にわたり武田家・武田信玄・武田勝頼に苦しめられた家康は、そこに気づきます。





信玄公の
真似をしよう!
「とても大事なこと」に気づいた家康でした。
次回は上記リンクです。


