前回は「記述式問題の対策とコツ〜記述問題で思考力を増強・「思考力を判断したい」という記述問題出題者の考え・出来るだけ「考えていること」を簡潔に書く〜」の話でした。
採点基準をハッキリ公開する武蔵中:武蔵志望者必須の過去問集
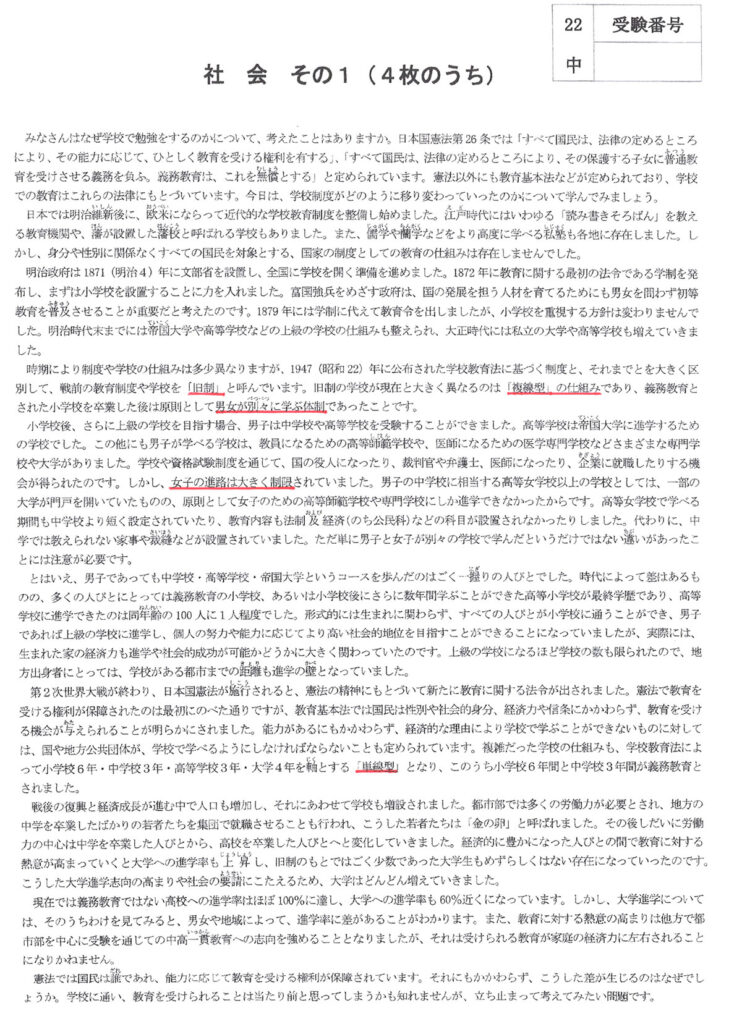
武蔵中・麻布中などでは、記述に非常に重点が置かれた問題が出題されます。
「答えだけ」を問う問題であれば、「何はともあれ解けること」が大事です。
一方で、記述問題は「明確な解答(模範解答)」がありますが、採点基準の詳細は不明であることが多いです。
そのため、「何が正解なのか」が不明瞭であることに対して、
 男子小学生
男子小学生結局、何を書けば
良い点が貰えるんだろう・・・
当事者である「受験生の立場」から考えると、不安を感じる方もいらっしゃるかも知れません。


例えば、武蔵中学校では学校側が「過去問・模範解答・採点者の考え」をまとめた過去問集を販売しています。
武蔵中学校を志望する方は、必ずこの「武蔵発行の過去問集」を買いましょう。
この「学校側が解答を明確に示す」姿勢は「試験を課す学校側の姿勢」としては大変好ましいことです。
この「好ましい」という感情は、僕が武蔵中高出身であることもあります。
それもありますが、公平に見ても「堂々としている」と誰しも感じるのではないでしょうか。



武蔵中の入学試験は
このような基準で採点しています・・・
この様にハッキリと世間に伝えることは、「方針を明確にする」点で極めて重要なことです。
中学受験・高校受験・大学受験では、「採点基準や採点方法」は非公開が多いです。
それは、大学生〜大人が受験する資格試験においても同様の傾向があります。
その中、



武蔵中では、入学試験を
このように考えています・・・
採点基準を「堂々と公開する」ことの意義は極めて大きいです。
この武蔵中高が「凋落した」と言われることに関する話は、上記リンクでご紹介しています。
昔と大きく異なり、東大合格者が激減した武蔵中高に対しては、



武蔵は
凋落した!



もう武蔵は
終わりよ!
このような声も多数聞かれ、現に武蔵卒の筆者も「これと近いことを言われた」経験があります。
こういう「武蔵凋落」の声を聞くとき、筆者は、



武蔵凋落など、
「余計なお世話」だ・・・



東大合格者が多いのは良いことかも
しれないが、だから何だ?
この様に感じているのが正直なところです。
現実として、武蔵高校の東大合格者数が「著しく減少」した事実は、OBとして大変残念であります。
一方で、このように「解答例をハッキリと受験界・世間に提示する」姿勢。
この姿勢は武蔵中学校の教育理念を明確にし、堂々としている点で「別格」と言えるでしょう。
自分なりのメモを書いて理解を深める


問5を考える時に、下記のような「まとめを書く」話をしました。
戦前(旧制):複線型(専門学校・大学、男女別)
現代(学校教育法):単線型(小学校〜大学)
このようにまとめることは、問5の後半で役立ちます。
後半がなくても、直前期は書いてまとめるようにしましょう。
そして、試験当日は「問題文を読んでいるうちに、まとめが頭の中に浮かぶ」のが良いでしょう。
当日も、簡単にこのようなまとめを書いた方が「問題に取り組みやすい」方もいるでしょう。
その場合は、余白に書いても良いでしょう。
そして、メモをもとに考えると記述でも選択問題でも「考えやすくなる」傾向がります。
「自分なりのメモ」を書いてみると理解が深まるので、学力も上がるでしょう。
単線型 = 進路が幅広い中から選べる
複線型 = 専門性が高く、選べる進路が限定される
特に武蔵中は、このような「欄外のメモ」があると、



よく考えていて、
とても良いね・・・
この様に「良い方向に評価」してくれる可能性があります。
そして、解答欄内の解答次第ですが「部分点として追加」してくれる可能性があります。
この「メモなどを評価する姿勢」は、記述式を課す麻布中などの学校も、そういう可能性があります。
1.東西文化融合のわが民族理想を遂行し得べき人物
2.世界に雄飛するにたえる人物
3.自ら調べ自ら考える力ある人物
武蔵中には、3つの教育理念があります。
上記リンクに武蔵中高の教育方針が記載されています。
旧制の頃に作成されたため、最初の二つの「東西文化〜」と「世界に雄飛〜」とあります。
これらは、1922年大正時代に設立された時、「外国が非常に遠かった」時代の名残があります。
少し古典的な言い回しですが、やはり「世界を見る視点」は大事です。
中高の基本理念において、最も大事にしている「自ら考えることの出来る人物」が欲しい武蔵。
「考えていること」は、どんどんアピールしましょう。
採点者が待っている答案:自分の考えを堂々と表現





でも、間違っていたら
どうしよう・・・
「間違っている」ことは「考えない」より「遥かに良い」のが武蔵中学の理念です。
まだ小学生で、これから中学・高校・大学・大学院・・・と学んでゆくのです。
だから、「間違っていても良い」のです。
それは、麻布中などの学校も同様と考えられます。(上記リンク)
「まとめ」を頭に思い描いても良いですし、ササッと走り書きでも余白に書いても良いでしょう。
そして、問5の後半では、「どのような書き方をするか」の話をしました。
「限定的」とややネガティブな書き方をするか、「進路を」をポジティブに書くか。
問題文に対する素直な姿勢:専門性が高く、選べる進路が限定される
やや自分の主観を入れた姿勢:早期に方向性を決めて高い専門性を学び、その中から進路を選ぶ
ポジティブな姿勢かネガティブな姿勢か、で解答の方針・カラーは異なります。
「どちらが正解」というのはなく、各個人の考え方となると考えます。



じゃ、どうやって
採点するの?
結局は、武蔵中なら「武蔵中の社会科教員の考え方次第」となります。(上記リンク)
麻布中なら「麻布中の社会科教員の考え方次第」と考えられます。



それでは、先生次第で
採点が変わるの?
基本的には「先生・教員次第」となるでしょう。
これが「試験の平等性を保つか否か」は、様々な意見があるでしょう。
一方で、この「採点の方向性」もまた各校のカラーや教育理念を示しています。
「採点基準や方向性」は「各校の教育理念」と同一方向であると考えられます。
そこで、「採点基準は教員次第」が正しいと考えます。
点数は気になりますが、採点基準を気にしても採点者が分からない以上、現実としては「不明」です。
とにかく、自分の意見をはっきり書きましょう。
すると、採点者は採点しながら、



うん・・・
なるほどね・・・
こう考えて、相応の点数を与えてくれるでしょう。



これは・・・
なかなか良いかもね・・・
採点者は、そういう答案を待っているのです。
次回は下記リンクです。







