前回は「「守護がトップの秩序」と天下人三人衆の家柄ランク〜朝廷の枢要に座り続けた中臣鎌足子孫の藤原氏・一気に巨大化した令外官征夷大将軍〜」の話でした。
日本史において680年ほど君臨し続けた「幕府」

日本の歴史において、長い時代存在したのが「幕府」という政治統治機構でした。
「幕府」という呼び方は、江戸時代後期に登場した説が有力です。
そのため、「三つの幕府の初代征夷大将軍」が存命した頃は「幕府」という言葉はありませんでした。
| 年号 | 出来事 |
| 1185年 | 源頼朝、守護・地頭を設置 |
| 1192年 | 源頼朝、征夷大将軍に就任:鎌倉幕府創設 |
| 1333年 | 鎌倉幕府滅亡 |
| 1336年 | 足利尊氏、征夷大将軍に就任:室町幕府開設 |
| 1573年 | 室町幕府滅亡(諸説あり) |
| 1603年 | 徳川家康、征夷大将軍に就任:江戸幕府開設 |
| 1867年 | 徳川幕府滅亡(大政奉還) |
鎌倉幕府成立に関しては、「守護・地頭設置の1185年」とする考え方もあります。
筆者は「征夷大将軍就任という形式」が重要と考え、「1192年が鎌倉幕府創設」と考えます。
ここで、以降の室町・江戸幕府の「開設」と鎌倉幕府「創設」と言葉を分けたのは理由があります。
それは、鎌倉幕府が最初の「幕府(言葉は当時なし)という政治統治機構」を創り出したからです。
途中の室町幕府滅亡に関しては、「織田信長による将軍・足利義昭の追放」です。
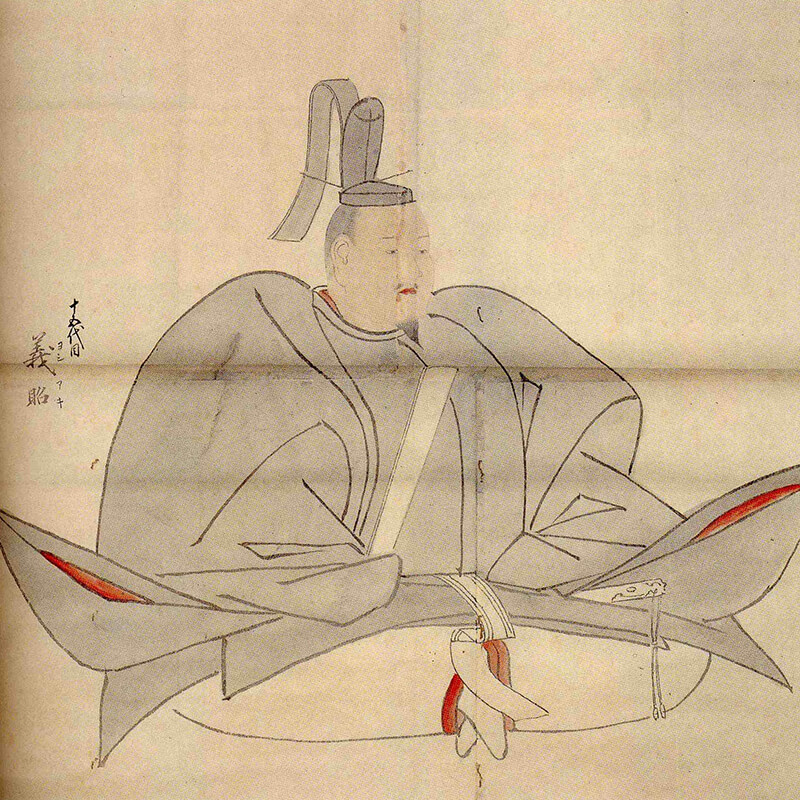
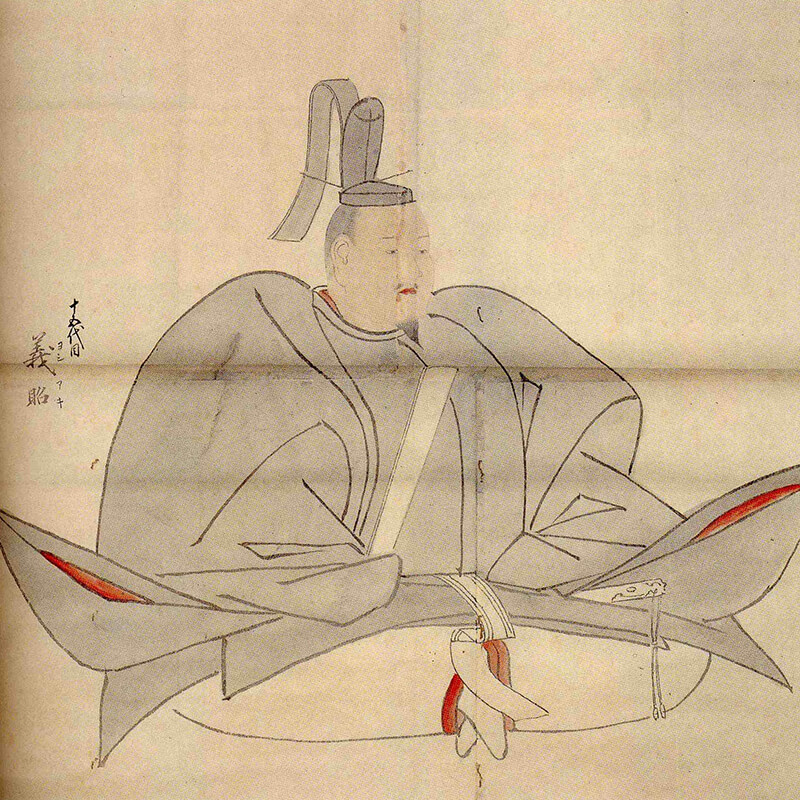
信長め!
将軍を京から追放するとは!
ただし、この後も「足利義昭は征夷大将軍であり続けた」のが歴史の事実です。
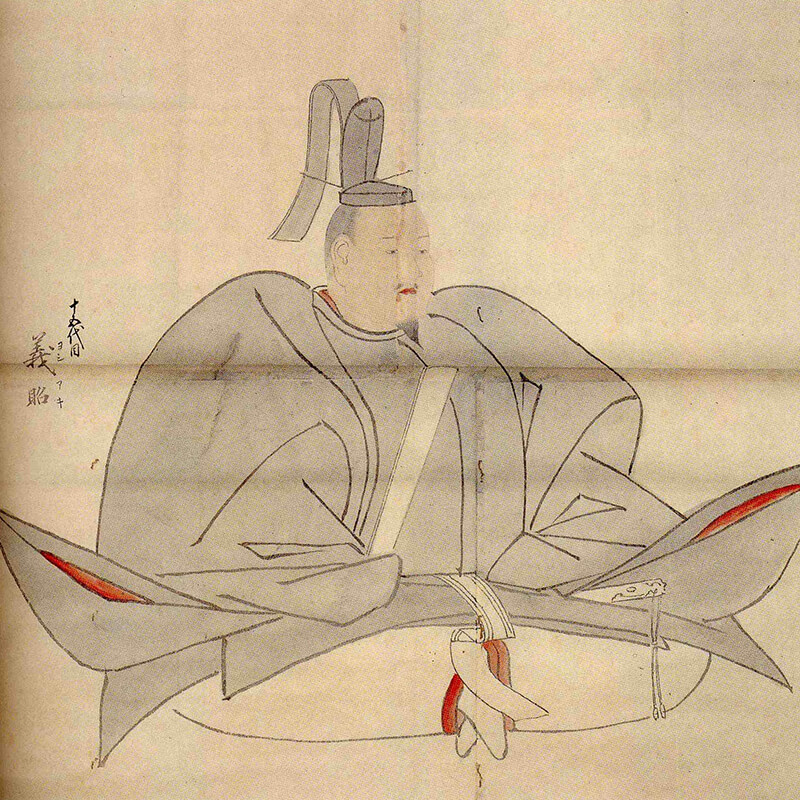
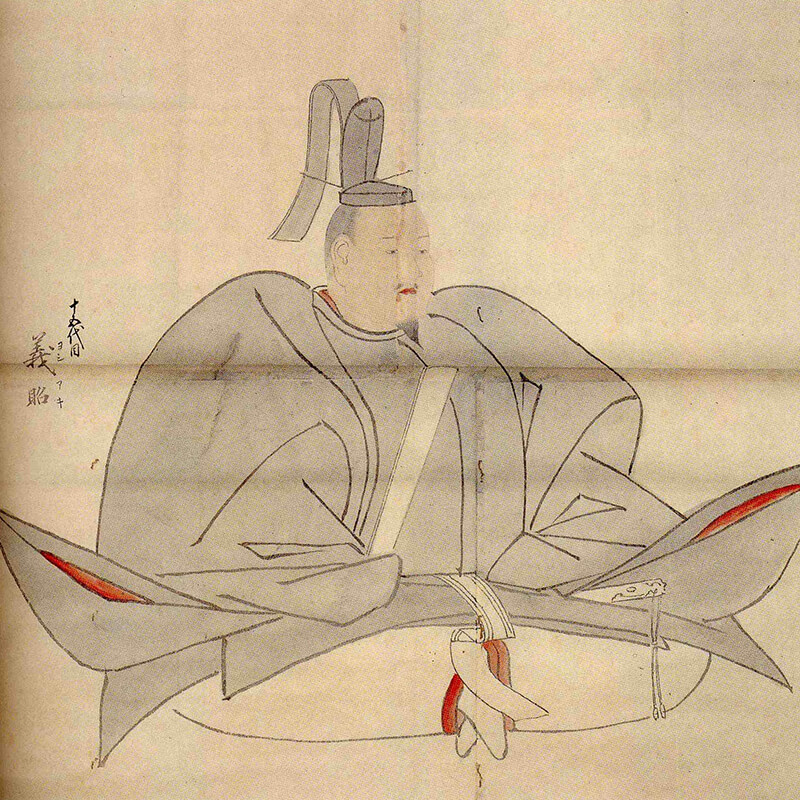

ならば、政治の中心を
移動して、我が政治を続けるまで!
そして、征夷大将軍として足利義昭は、備後の鞆という場所で「政治を続けていた」のでした。
ただし、たいした権限もなく、なんとなく「足利将軍が政治しているつもり」だったのでした。
そのため、上の表では室町幕府滅亡に「諸説あり」と記載しています。



この家康が
戦国の世を終わらせる!
そして、徳川家康によって、「最後の幕府」である江戸幕府が開設されたのが1603年です。
1192年から1867年までの680年ほどの間、日本に君臨し続けたのが「幕府」でした。
守護の格式から「徳川の格式」へ
Daimyo_I104ts
そして、元は「松平」という名字だった「徳川」は、元々は「大した家柄ではない」存在でした。
鎌倉時代のスタート時期に生まれた「守護」という役職。
Daimyo_B107ts
守護は、当時の日本におけるそれぞれの国(現在の都道府県)の最高権力者でした。
「各国の最高権力者」という権力が生まれ、一定の時間が経過すると「格式」が生まれました。


戦国時代に大大名となった武田・島津・大友などは、元々守護であり、絶大な格式を持っていました。
「戦国時代の華」である1560年〜1580年頃は、守護が生まれてから400年近く経過していました。
「400年間残っていた」守護の格式は、400年の間に「圧倒的な格式」となっていました。
Daimyo_J101ts
今回は、戦国時代に続く、「最後の幕府」となった徳川幕府における格式を考えます。
頂点に君臨するのが「徳川本家=将軍家」でした。
そして、それに続くのが「御三家」でした。
hs11_143ts
御三家は、いわば「徳川本家=将軍家直属の親衛隊」の役割を持っていました。
「御三家」に関わる中学受験・社会の問題に関する話を、上記リンクでご紹介しています。
Daimyo_J102ts
「御三家」は徳川本家よりは格下となりますが、「将軍を輩出することが出来る」格式を持っていました。
そして、諸大名の間における江戸城の扱いは、御三家は文字通り「別格の扱い」を受けました。





御三家の紀伊から
この吉宗が新たな将軍になる!
八代将軍・吉宗は、「徳川本家の血筋が続かなかった」為、御三家の紀伊から将軍家となりました。
この時点で、御三家は「徳川本家=将軍家と同格になった」と考えられます。
御三家:紀伊・尾張・水戸
御三卿:田安・一橋・清水



御三家だけで
将軍家の血筋を守るには不安がある・・・



御三家の下に
御三卿を設立する!
そして、生まれは御三家・水戸である御三卿・一橋からは、「最後の将軍」が誕生しました。





私は御三家である水戸出身だが、
一橋家から将軍になったのだ!
徳川幕府の末期において、御三卿の家格は一気に上がり、「御三家同等」に近くなったと考えます。
ところが、「徳川の時代」は、慶喜の時代にジ・エンドとなりました。
そのため、「御三卿の家格」は、急上昇してすぐに徳川の時代は終了してしまったのでした。
徳川慶喜に関する話を、上記リンクでご紹介しています。
「お山の大将」だった外様大名:政治の中枢は徳川と譜代
Daimyo_J104ts
そして、御三卿の下には、「徳川(松平)家の三河以来」の譜代大名がいました。
いわば、「ずっと徳川(松平)家一本の家柄」が譜代大名でした。



私たち譜代大名は、
ずっとずっと徳川一本です!
譜代大名は需要な地を任され、「徳川中心の幕藩体制の屋台骨」となることが期待されていました。
そして、譜代大名には、井伊家を筆頭に大老を輩出した「大老四家」がありました。





不逞(ふてい)な連中を
まとめて処分する!
1858年の安政の大獄を引き起こした、大老・井伊直弼の井伊家は「御三家と同格に近い」家柄でした。
| 家名 | 人数(名) |
| 井伊 | 5 |
| 酒井 | 3 |
| 土井 | 1 |
| 堀田 | 1 |
井伊直弼以前の大浪出身の家柄が上記であり、直弼を入れると「井伊から6名」です。
Daimyo_J105ts
譜代大名の下には、主に「関ヶ原」以降に徳川家に従った家が続きます。
彼らは「外様(とざま)大名」と呼ばれ、名称からして、いかにも「部外者」扱いでした。
外様大名には、前田・島津・伊達など石高が高い大名も多数いましたが、



徳川幕府の中枢には、
信用できる譜代に任せる!



外様大名は「お呼びでない」ので、
参勤交代してなさい!
外様大名の格式は、譜代大名から「かなり下」だったのでした。
Daimyo_J106ts
江戸時代の各藩・各家の格式をランク付けすると、上のようになります。
このランク付けは筆者独自の視点であり、様々な意見があるでしょう。
つまり、「Aランク(譜代大名)以上」が、徳川幕府の主流でありました。
そして、外様大名は「譜代大名である老中や大老に従う」存在でした。
外様大名は国家運営に関われず、諸外国との折衝も禁止されており、



外様大名は、国元で
大人しくしていなさい!
大きな領土を持っていても、言わば「お山の大将」の扱いだったのが外様大名でした。
次回は上記リンクです。




