前回は「プラモデルの仕組の理解と想像力〜物を作ることの楽しさ・子どもなりに気づくプラモデルの特徴〜」の話でした。
大人も楽しい「ガンダム三国志」

「ガンダム三国志」のプラモデルは、未就学児のプラモデル作りに最適です。
三国志に興味がある方にとっては、様々なキャラクターがリアルに表現されていて面白いです。
こういう「三国志シリーズ」では、定番の曹操・劉備・関羽・張飛以外にも、
 内野吉貴
内野吉貴これが典韋か・・・
確かにそんな感じだ・・・
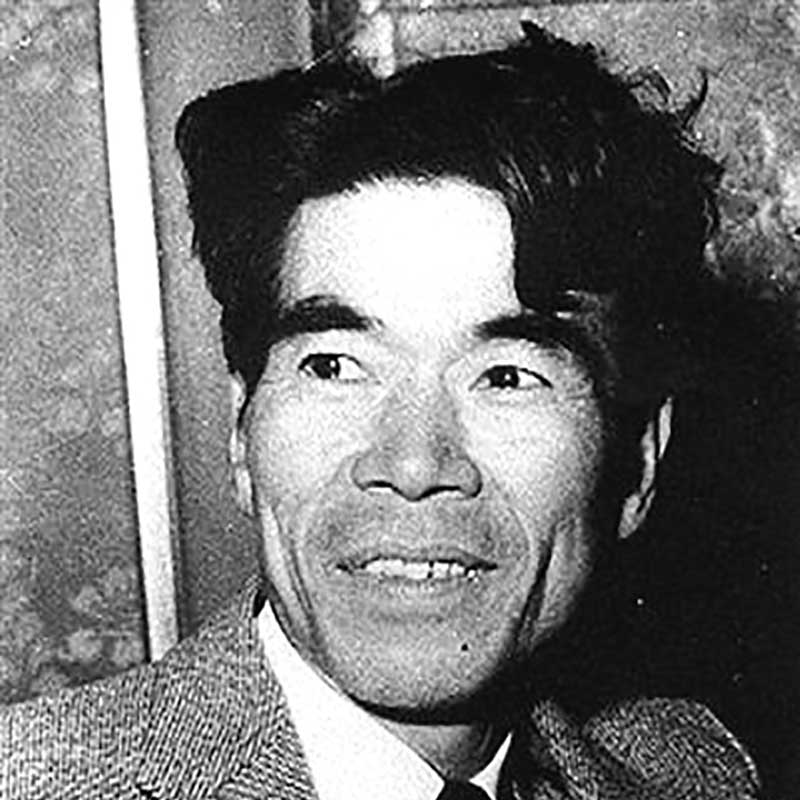

筆者は中学生の頃に、吉川英治「三国志」を何度も読みました。
1990年初頭は、光栄(現コーエー)の歴史シミュレーションゲームが大ブームでした。
その影響もあり、書物の「三国志」もまた、大ブームでありました。



暗記してしまうほど、
読みました。
懐かしくなり、子どもと一緒に、



この夏侯淵も
面白いから作ろう!
「子どものため」というよりも、自分が楽しんでいる感じです。
1990年初頭のゲーム「三国志II」の話を、上記リンクでご紹介しています。
時には、バラバラになってしまうこともあるプラモデル。
こういう時、



これ、もとに
戻せるよ!
子どもは、子どもなりに理解していて「一度作った体験」で復元できます。
子ども〜青年の頃作っていた方の多くが、大人になると「作る機会」がグッと減るプラモデル。
筆者も、プラモデルを作るのは、実は10年以上振りでした。
「おもちゃ」といえば、おもちゃですが、「つくる」というプロセスがあるのが大事だと思います。
「自然と進む理解」とプラモデル作り


今回も、ガンダム三国志シリーズを作ってみましょう。
今まで、関羽・呂布・劉備・曹操・孫堅など作りました。
いわゆる「メインキャラ」達ですが、今回は荀彧です。
子どもがパッケージを見て、



これ、
かっこいい!
こう決めたのですが、



荀彧も
あるんだ・・・
荀彧は曹操の参謀・軍師役ですが、諸葛亮とは違って、あまり戦場には関わってないからです。
とは言っても、子どもが「好き」なのが良いので、荀彧に決定しました。


まずは、頭から作成して、続けて胴体を作ってゆきます。
このシリーズは、基本的な「つくり」は共通しています。
慣れてくると、あまり説明書読まなくても、子どもは作ってしまいます。



説明書、
読まなくていいの?



うん!
大丈夫だよ。



似てるから、
分かる。
子どもなりに、共通点を自然に把握しています。
このように「自然と理解が進む」ことが、学ぶプロセスにおいては大事なことです。
「理解しよう!」「覚えよう!」と考えることも大事です。
一方で、算数や理科においては「自然と進む理解」が大事だと思います。
プラモデルを色々な角度から見る体験


プラモデル作る時は、どんどん先に行きたくなりますが、作っている過程も楽しみましょう。



ちょっと違う角度から、
見てごらん。



うん・・・
こうして見ると・・・



なんか、
面白いね・・・
具体的でなくても「何か面白い」という気持ちが大事です。


胴体と腰の部分が出来ました。


両手・両足もできてきて、後は合体です。
このシリーズは、全体的な構成・関節部分は共通しているパーツが多いです。
この共通パーツによって「合理化されて」いるのが、良く分かります。
そして、各武将の個性・カラーを全体像と細かな部分で表現していて、非常に凝った作りです。


完成しました。



できた!
遊ぶ!
黒い銃を二つ持って、赤いゴーグルしたガンダムです。


プラモデルは、完成したら、色々な角度から見てみましょう。



ほら、ここが、
こうなっているよ。



へえ〜、
面白いね。
中学生以上になると、プラモデルは「作ったら、飾る」ですが、小学生は遊ぶのが好きです。
その過程で色々な角度で見ていますが、「意識してみてみる」と面白いです。
「パーツがどのように繋がっているか」「影がどのように変わるか」など。
「立体ならではの面白さ」が、プラモデルにはあります。
この「立体であること」が、二次元の絵やテレビと大きく異なることです。
「立体を楽しむ」姿勢が「立体感覚」を磨くでしょう。
すると、少しずつ算数も得意になってゆくと考えます。
次回は上記リンクです。



