前回は「「偏差値を上げる」ことはプロセスの一つ〜合格という目標・考え方や解法を「自分のものにする」学び」の話でした。
30〜40年前の中学入試問題と現代中学入試問題の難易度

今回は難関校〜最難関校の中学受験の「問題の難易度」に関する話です。
中学受験は、実に様々で難解な問題が出題されます。
 内野吉貴
内野吉貴こういう問題を、
試験時間内に出来るようになるように勉強する・・・



勉強する受験生・
子どもたちは本当に大変・・・
「中学受験生は大変」と思います。
大学院生の頃まで、小学生から高校生を教えた経験がありますが、もう15年以上前です。
新教育紀行を書き始めたのは、きっかけがありました。
それは長男が小学校一年生になり、「子どもの学び」を目にして、



子どもの教育にとって、
何が一番大事なのだろう・・・
「教育で一番大事なのは何か」と考えたことでした。
世の中では中学受験の盛況が続く中、問題全体の全体の難化が指摘されています。
中には、



30年前の開成レベルの問題が
偏差値40の学校で出る・・・
このような声もあるほどです。
つまり、僕たちが中学受験した頃の「最難関の開成中の問題」が「現代では普通」ということです。
「偏差値40」というのは「平均以下」という評価です。
つまり、「30年前の最難関の開成中の問題」は「現代では易しい」となります。
このことから、



30年前の中学受験経験者の状況とは
全然異なる・・・
「30年前とは全然違う」という意見があるようです。
昔と大きく変わらない中学受験の問題
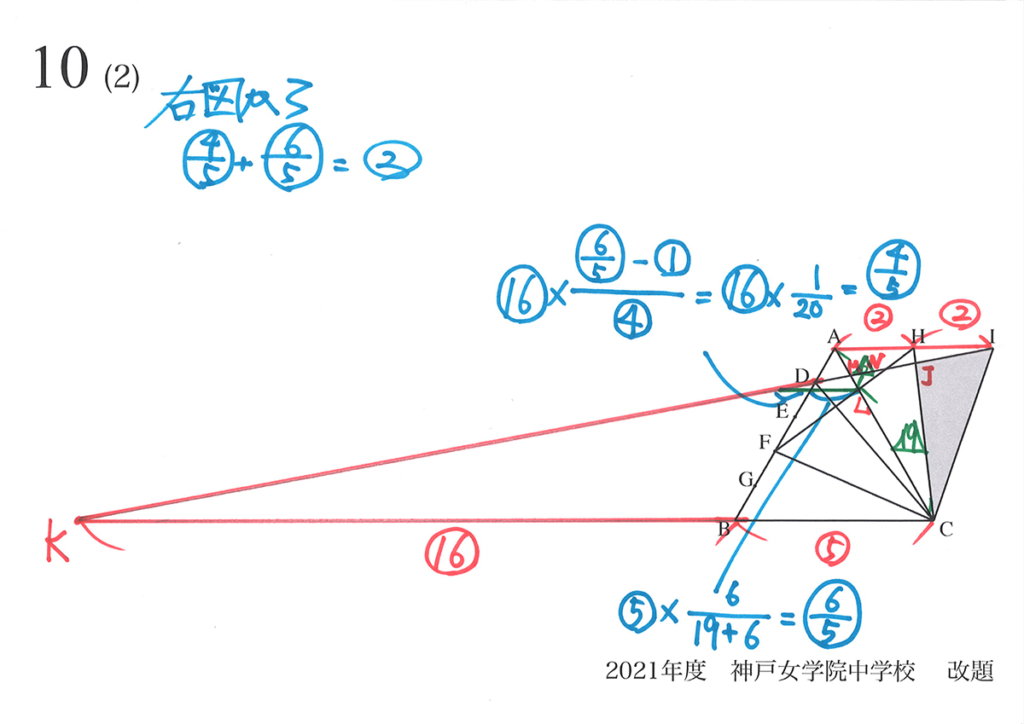

確かに1980年代にバブル経済へ至る高度急成長時期に、中学受験が加熱化した時期から40年ほど。
この40年の間には中学受験では実に様々な問題が出題され、受験界は研究しているでしょう。
実に多様な問題が出題される中学受験ですが、基本は「小学生が学ぶ範囲」が対象です。
どうしても「範囲はある程度限定される」ので、そのバリエーションは限られるように感じられます。
この中、各中学校の入試担当者は、一生懸命に問題を作成していると思われます。
筆者は1977年生まれで、1990年に中学受験しました。



1977年生まれなら、
同い年だ!
あるいは、



年齢が
近いわね。
このような親の方も大勢いらっしゃると思います。
「30年以上前に中学受験した」のが筆者です。
昔は数学が「かなり得意」でしたが、しばらくやってないので「解く力」は大きく落ちています。
中学受験の難しい問題を見た時、



これは、
ちょっと分からないな・・・
「難しい」と思うことも多々あります。
問題を色々と見ていると、



ああ、
面白い問題だな・・・
こう思ったりしますが、



昔と大して
変わらないかな・・・
「大して変わらないな」というのが、問題を見た実感です。
受験界の一部で言われている、



30年前の開成レベルの問題が
偏差値40の学校で出る・・・
この声を直訳すると、



30年前の開成レベルが
今の偏差値40レベル・・・
こう取れる話です。
出題が多様化している中、実に多様な考え方を身に付けなければならない受験生。
この視点で考えれば、「30年前の開成レベル=今の偏差値40レベル」になるかもしれません。
一方で、これは「解法パターンを身につける」考え方が主軸と考えます。
「しっかりした考え方を学んで解く」姿勢の場合、難易度はさほど変わらないのが実態でしょう。
中学入試した親と「今の中学入試」:基本をきちんとしっかりと学ぶ


現実は「30年前も今も問題の質・難易度は大して変わらない」と考えます。
「新鮮味があった問題」が、たくさんの学校で類題が出題されることがあります。
その結果「新鮮味」がなくなり、「ありふれた問題になった」場合は中学受験〜大学受験で多数あります。
基本をきちんと学べば、特に算数は必ず出来るようになると考えます。
この点で、「30年前とは違う」とは思わない方が良いでしょう。
「解放テクニックの積み重ね」で考えると、長い中学受験の多数の問題が受験生に負担になるでしょう。
30年〜40年前に中学受験をした親は、無理に自らの価値観を押し付けず、



基本をきちんと・しっかりと
学んでゆくのが良いんだよ・・・
こう伝えて、子どもに実行してもらいましょう。
きっと受験生本人の学力が着実に上がってゆくでしょう。
次回は下記リンクです。



