前回は「おすすめの子どもの読書習慣と学力アップ〜スマホで撮影・ノートやメモを取らない「学んでいない」姿勢・コストがかかった昔のカメラの「現像」と無料のスマホ・便利さの裏側・撮影することと「書いて・描いて」学ぶこと・効率と非効率〜」の話でした。
大きな本を読む体験:図書館仕様の特別本の存在
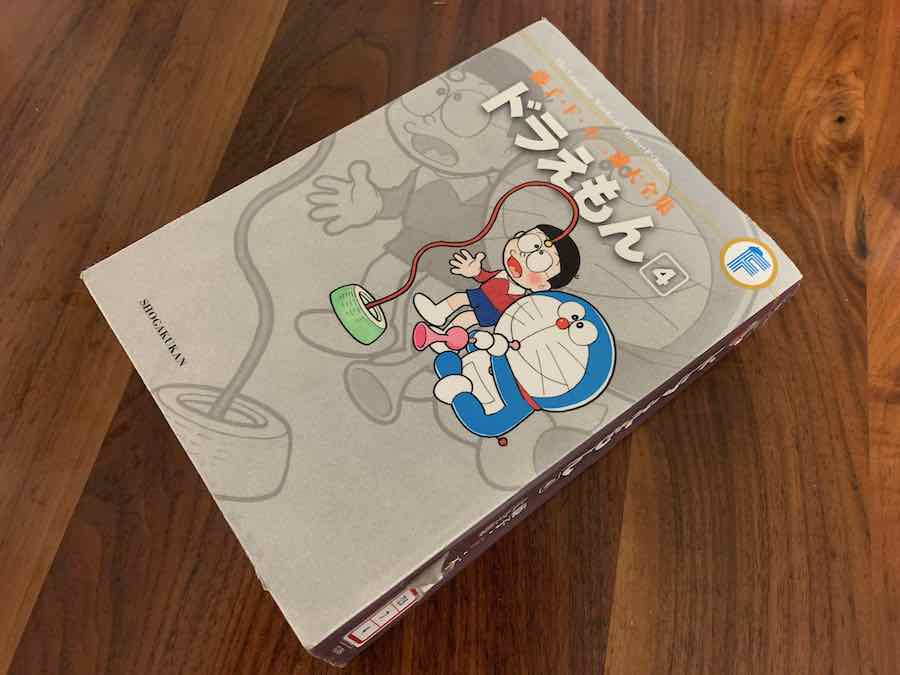
子どもと図書館に行った際に、借りた本の一つが上の「分厚いドラえもん」です。
厚さ3cmくらいあって、なかなかのボリュームです。
一般的なサイズの「ドラえもん」は、自宅に置いてある家庭も多いです。
この豪華版・全集を自宅に置いている、ご家庭は少ないと思います。
その意味では「図書館仕様」とも言える本です。
子どもは見たらすぐに、
 子ども
子どもこのドラえもん、
借りる!
小学生が「ドラえもん」を見たら、大抵即決になります。



「ドラえもん」は
久しぶりだけど、結構面白いな・・・
読んでみたら、結構面白い話もあります。
少し重いですが、「どっしりした感覚」が、「読書している感じ」で面白いと思いました。
書籍には図書館仕様「図書館にしか置いていない形式の本」があります。
小さな子向けですが、とても家庭には置くことができないような超大型の本もあります。



この本、
とても大きいね・・・



ちょっと
読んでみようか。
あるいは表紙・裏表紙が分厚くなっている図書館仕様本があります。
分厚くなっている理由は、「多くの子どもたちが触れても傷みにくい」ようになっているからです。
そうした「図書館だけの体験」もまた、読書の大いなる体験になるでしょう。
想像力と読書:映像・音声・文字の情報量の大きな違い
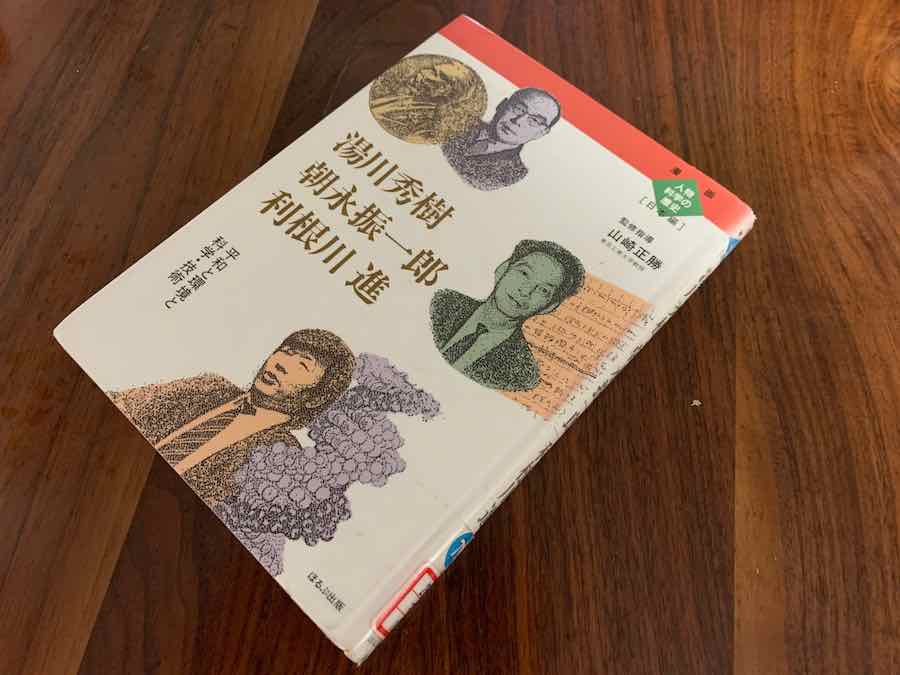

酒井東大大学院教授によると、読書を情報を置き換えた様々な研究に関する結果が紹介されています、
文字で読む・音声で聴く・映像で見るでは、脳に入力される情報量に大きな違いがあります。
情報量を比較すると、映像・音声・文字の順に減少します。
| 情報形式 | 情報量 |
| 映像 | 大 |
| 音声 | 中 |
| 文字 | 小 |
確かに文字は「文字でしかない」とも言え、映像は画像と音声があり、情報量は多いです。
その代わりに、「情報量の少ない」文字の場合は、「足りない部分を想像力で補おうとする」のです。
「言語野の四領域を総動員」して、想像力で補おうとするようです。
「言語野」は詳しくは知りませんが、「想像力で補おうとする」のは非常に分かります。
特に映像を見ていると、「映像と音声を理解する」ことで手一杯になります。
どうしても「受け身の姿勢」になります。
一方、文字で読んでいると「行間を読む」がごとく自分で色々と想像します。



これは
どういうことだろう?



これは、
こんなイメージかな?
読書によって想像力と創造力が少しずつ磨かれるでしょう。
・実際見ることが出来ない顕微鏡の拡大写真や遠い地域の写真で想像力を上げる
・空想の世界で様々考えて、創造力を上げる
手を動かして学ぶこと:「見て理解」より「書いて描いて理解」
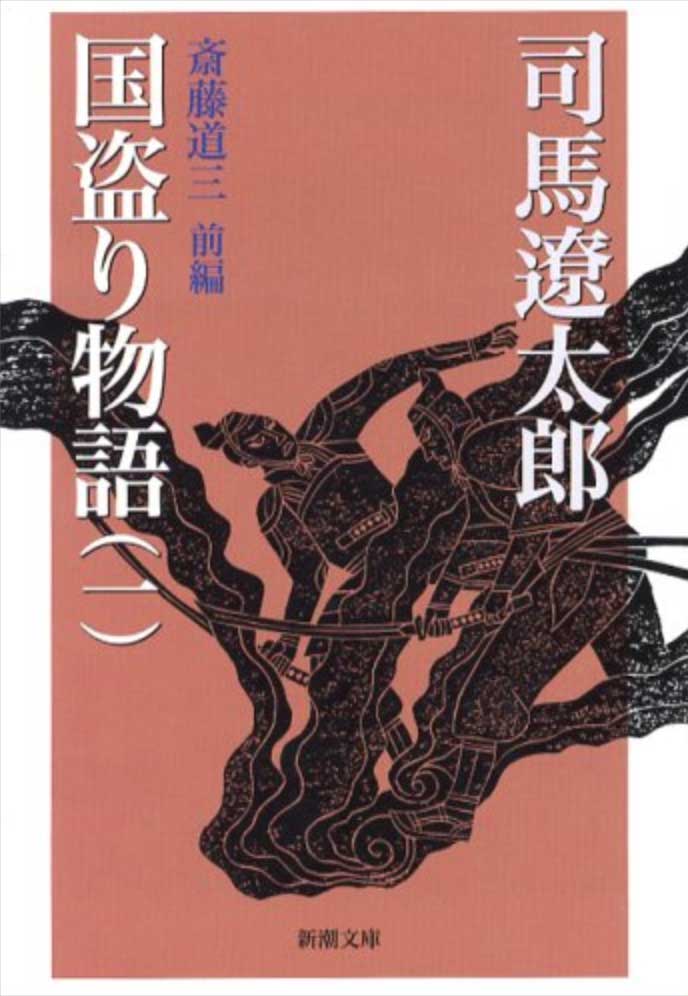

歴史が好きな筆者は中学生〜大学生の頃に、司馬遼太郎さんの本は、かなり読みました。
中でも、最初に読んだ「国盗り物語」は一番好きです。


そして、読みながら織田信長や斎藤道三、あるいは明智光秀のイメージを勝手に作り上げます。



信長の顔は、
こんな感じかな?



真面目そうな光秀は、
こんな感じ?
これらの雰囲気は肖像画のイメージと似ている部分もありますが、「勝手に作り上げたイメージ」です。
そうした「自分で勝手に作るイメージ」が「想像力を鍛える」のでしょう。
中学受験・高校受験・大学受験の方は、



この図形問題は、
補助線を描いて色々試してみよう・・・



この文章題は
長いから、図解して整理しよう・・・
面倒がらずに「手を動かして、しっかり理解する」を実践してみましょう。
・「図や絵を描く」ことを大事に
・上手くなくて良いので、丁寧に描く
・図形問題の場合、「図形全体と補助線」を描く
自然と、少しずつ学力が上がるでしょう。
「動画などを観て勉強」することは良いことですが、実際に学力を上げる必要があります。
情報量がとても多い動画・映像は、受け身になって「理解したつもり」になりがちです。
・「見て理解」したことは、あまり頭に残らない
・「描いて理解」したことは、頭脳にしっかり刻まれて発展する傾向がある
描いて理解することを着実にこなしてゆけば、学力が上がり、成績も上がるでしょう。
次回は下記リンクです。


