前回は「記述問題の攻略法 1〜大事なポイントとコツ〜」の話でした。
水溶液の実験のポイント:食塩が水に溶ける様子を描く
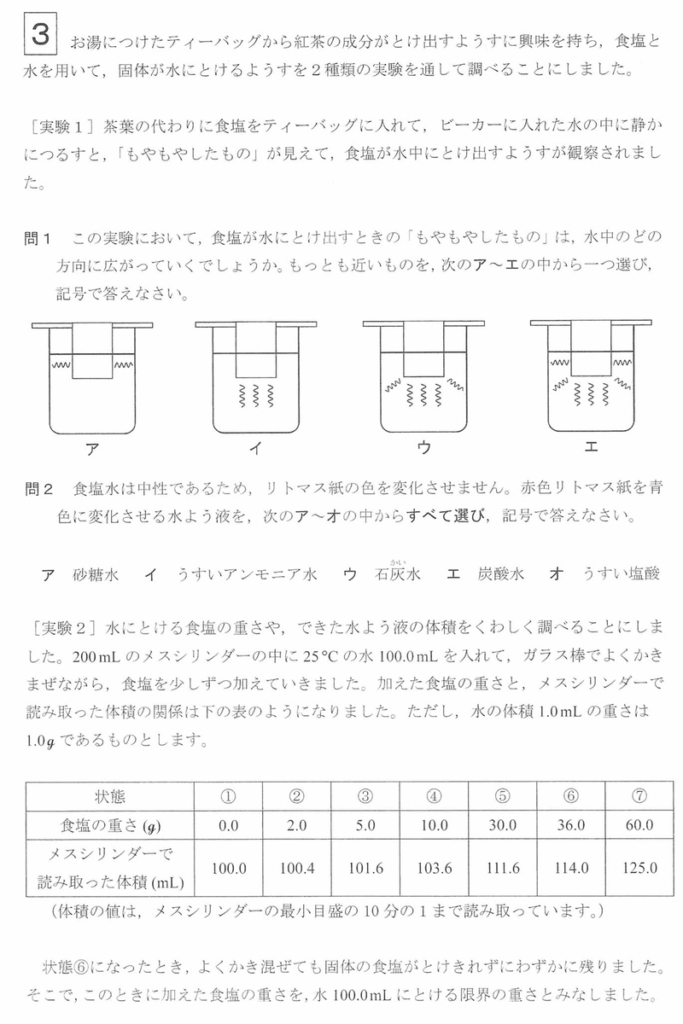
今回は、開成中学校の2020年理科の問題3を考えてみましょう。
食塩を水に溶かす問題で、まずは前半を考えてみます。
問1では、食塩が水に溶け出してゆく状況が問題です。
こういう「溶かす」などの場合は、溶かすもの=食塩を問題に記入してみましょう。
・「溶かす」などの時は、溶ける物質などを描く
・実験の対象となる現象を描いたり、具体的にイメージする
 男子小学生
男子小学生どうやって、
食塩を描くの?



食塩は
小さいから、描きにくいよ・・・
小さな点などで、食塩などの物質を表現すると良いでしょう。
そうすると、何となく溶けてゆく感じがイメージできます。
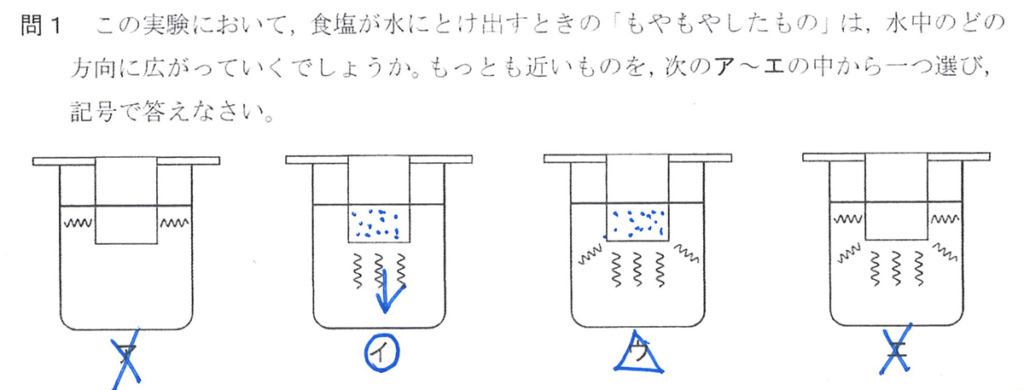

頭の中でできるかと思いますが、実際に描いてみると「溶け出してゆく感じ」がわかります。
まず、重力で下に落ちるはずですから、アとエは✖️です。
イ、ウが残り、ウはあながち間違いではない感じもします。
ウは、斜め45度の方向に食塩が溶け出してゆく感じです。
ここで考えてみましょう。



食塩が溶けて、
下と斜め45度に広がってゆく・・・
何らかの外からの力などがない限り、ここまで斜めにはならなそうです。
「斜めに落ちる」としても、「もう少し斜めではない方向」なはずです。
ここで、



重力がかかるから、
物質は下に落ちるね。
「物は下に落ちるはず」と考えてイが答えです。
イ
こういう時は、実際に食塩やボールを落としてみることをイメージしましょう。
・状況を頭に具体的に思い浮かべる
・物質の広がり、動きなどは、「どうなっているのかな?」「どうなるかな?」を考えてみる
水溶液の性質をイメージ
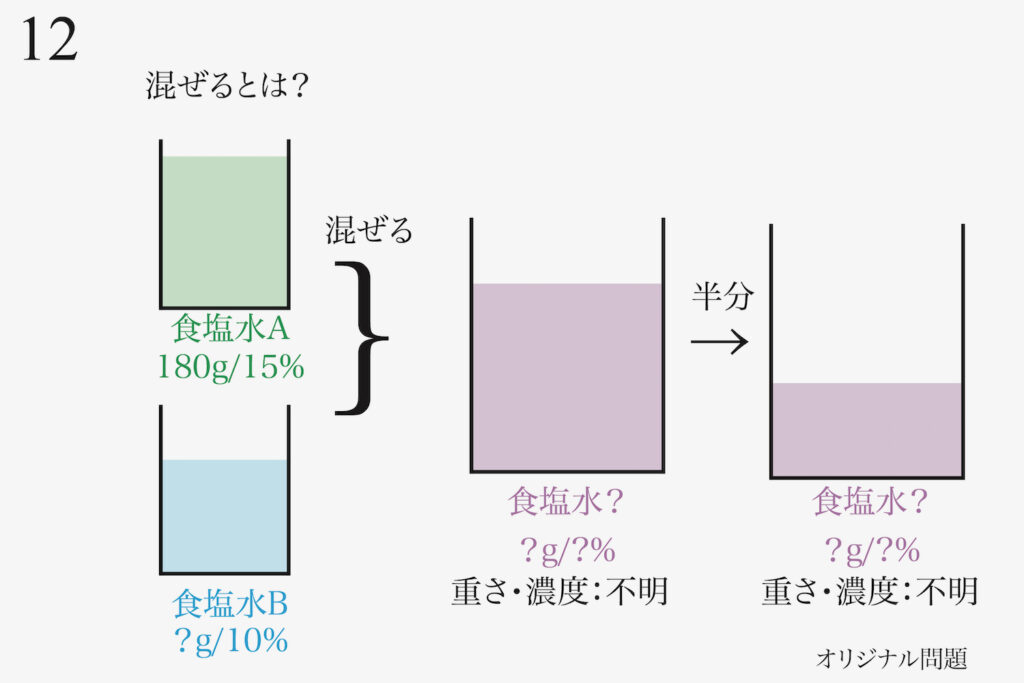

水溶液の問題は、「食塩水の濃度の問題」などで算数でも登場します。



理科の問題だけど、
算数っぽいところがあるね・・・
このような実験問題をしっかり理解すると、算数の学力も上がります。
問2では、赤色リトマス試験紙が青色が出ます。
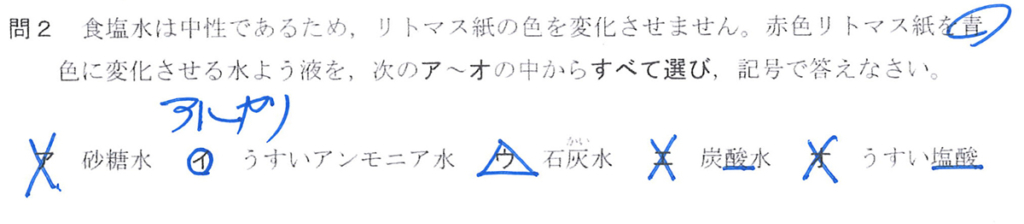

青にマークして、



よし、
アルカリだ!
「アルカリ」と問題文に書いてみるのも良いでしょう。
エ、オは名前に「酸」が入っている通り、酸性なので✖️です。
アの砂糖水は、酸でもアルカリでもないので✖️です。
イのアンモニアは、アルカリであることは知っている方が多いでしょう。
ウの石灰水は「アルカリ」です。
もし知らなくても、ここまで絞って「全て選ぶ」だから複数ありそうだから、



ウも
答えかな?
こう考えてみるのも良いでしょう。
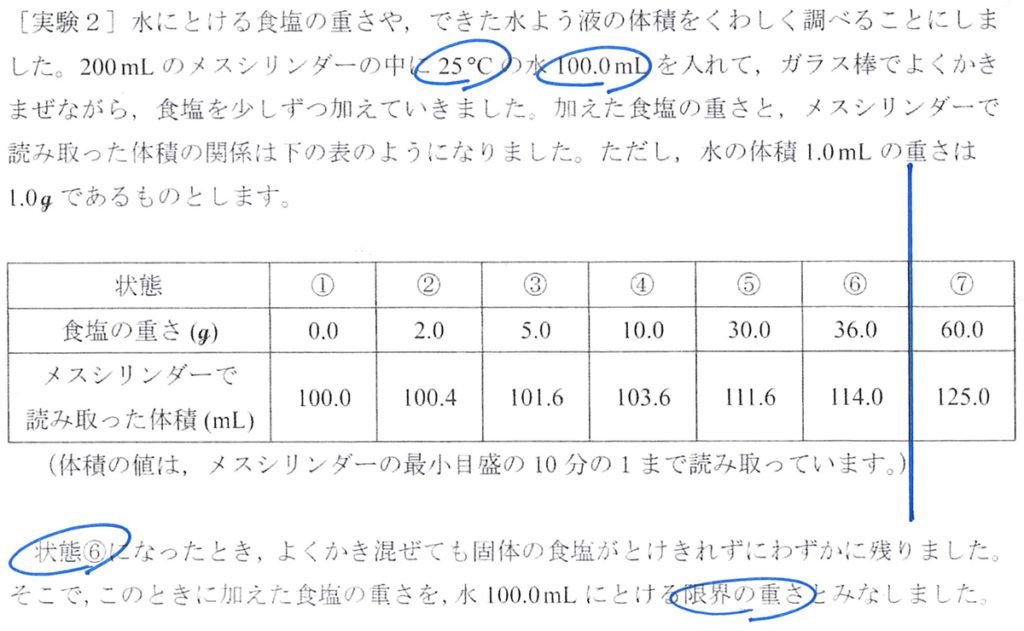

イとウ
大きな変化をチェック:理科実験を思い出す


実験2に進みますが、25℃、100ml等キーワードは○などで囲って意識しましょう。
・大事な数字・数量などは○で囲んで、意識する
状態6になったら、食塩が溶けるのが「限界になった」とありますから、「限界の重さ」に○します。
こういう表が出てきて、「溶ける限界」などの「大きな違いが出たとき」は、大事なポイントです。
上図の通り、自分でその境界に線を引きましょう。



この前後で、
全然状況が異なる!
・状況が変わる前後を発見する。
・発見した「状況が変わる時、場所」に線を引いて、明確に意識する
上記の様に、選択肢の問題でも問題文に描きこんで、イメージを膨らましてみることが大切です。
小学生のみなさんは、学校などで理科実験をしたことがあります。
このように「食塩を溶かす」などは具体的で頭でイメージしやすいのです。



小学校の理科実験を
思い出す・・・
「食塩を書いてみる」とあたかも実験室にいるかのイメージとなり、問題に取り組みやすくなります。
すんなりと答えがわかる場合は、時間がかかるので、描きこむなどはしなくても良いでしょう。



あれ?
どうしようかな?
悩む時は、このように「描いてみる」と良いでしょう。
「食塩は真下に落ちる」などの具体的イメージに結びつき、少し余計に時間がかかるかもしれません。
具体的イメージを描くと、正答率があがるでしょう。
次回は下記リンクです。


