前回は「守護代を支えて各地で力を付けた者たち〜「わずか三代で終了」した源氏将軍・明治維新以前の最大の変革・「下が上を消す」下剋上〜」の話でした。
徐々に下へ権力移行した室町末期から戦国時代
Daimyo_D104ts
鎌倉幕府創立者・源頼朝によって、形作られた守護による各国支配体制。
「各国トップの守護を任命するのが、頂点にいる鎌倉幕府」というシンプルな機構でした。
守護は「他の国も兼ねる」こともあり、様々な意味から「補佐役」を必要としました。
Daimyo_E107ts
そこで、鎌倉末期〜室町期頃に、各国で守護代が誕生しました。
守護代の任命は、中央政府である幕府が直轄する場合もありましたが、
 守護X
守護X我が配下のAは、
有能で、力もある・・・



Aを守護代として、
補佐してもらおう・・・
守護が直接「代官として」守護代を任命したケースもあったと思われます。
現代の都道府県に相当する「国」を治めるためには、どうしても重層的な支配機構が必要です。
現代の各都道府県知事よりも、遥かに巨大な権力を持っていた存在が守護でした。



我が国の各地それぞれを
有力者に任せたい・・・
大きな国ほど「国の各地域」を治めるためには、地域の有力者がいた方が統治しやすいのは当然でした。
中には、「守護が衰退してしまう」ケースもあり、守護代はメキメキ力をつけてゆきました。
Daimyo_F105ts
さらに、守護代の下(守護代重臣など)の存在が力を持つケースも登場し、



これからは、
我らYに国を治めさせてもらおう!



守護代Yの方が力が
強いから、やむを得ん・・・
守護代が、守護に取って代わる「下剋上」の世の中になりました。



これからは、
我らZに国を治めさせてもらおう!



我が家臣Zの方が力が
強いから、やむを得ん・・・
すると、今度は「守護代が取って代わられる」事態も登場し、世の中は混乱し、戦国時代となりました。
戦国時代の象徴となった「桶狭間」:松平から徳川へ
Daimyo_G101ts
今回は、守護代の下の守護代重臣のさらに下の国衆(くにしゅう)・地侍(じざむらい)の話です。
日本全国において、当時、「地域のまとめ役」として国衆・地侍がいました。
国衆は「国人(こくじん)」と呼ばれることもあります。
「地侍」という言葉は、「地域に根ざした侍たち」という意味です。
Daimyo_G102ts
国衆出身で、戦国期に大大名化した家として、松平・伊勢・毛利の各家があります。
三河出身の松平家は、のちに徳川家と名前を変えて、徳川家康が天下を握りました。


「下剋上」で「実力主義」だった戦国時代でしたが、「権威」の力はまだまだ残存していました。


その中、名門の守護であり、強力な戦国大名であった今川義元が、織田信長に討たれてしまいました。



まさか、
この守護の超名門今川が・・・



尾張守護代の下の
織田家なんぞに・・・
1560年に勃発した桶狭間の戦い以前から、各地で「下が上に取って代わる」現象が起きていました。
その中、この「守護・今川家」が「守護代の下・織田家」に潰された驚天動地の出来事。
この出来事こそが、戦国時代の一つの象徴となりました。



今までは、今川家の
従属大名の立場であったが・・・
三河の国衆であった松平家は、一応「一城の主人」でした。
松平家は、今川家から見れば「守護・守護代・守護代重臣・国衆」で3ランク下でした。
本来ならば、強力な今川家には、「義元の後継者・氏真を補佐する体制」が整っていましたが、



氏真様では、
戦国の世を切り開くのは無理・・・



ここは、独立して
元の三河国衆・松平を再興するか・・・
1543年生まれで「今川家の子分」だった松平元康は、当時満18歳で「若過ぎる」存在でした。



松平殿・・・
ここは我らと手を組まぬか?
悩んでいた元康の元に、「主筋・今川を討った仇敵」織田信長から同盟の打診が来ました。



・・・・・



よしっ、今川はもうダメだから、
織田殿と組もう!
ここで、悩みに悩んで上で、「今川と手を切り、織田と手を結ぶ決断をした元康。
Daimyo_G103ts
そして、心機一転「苗字を変える」ことを決断した松平元康。



今日から私の名前は、
松平元康から徳川家康へ!
そして、「苗字のついで」に「名前も変更」してしまったのが家康でした。
そして、「桶狭間」の40年後の「関ヶ原」で、家康は事実上天下を握りました。
各地で着実に力を蓄えた国衆たち
Daimyo_G104ts
そして、室町幕府の政所執事という名門・伊勢氏の一派であった伊勢新九郎。





どうやら、姉の嫁ぎ先の
今川家で内輪揉めしているらしい・・・



今川家で内紛が起きて、
我が子に危険が・・・



弟よ、駿河に来て
なんとか、内紛を収めてくれないかしら・・・



分かりました!
駿河にゆきましょう!
そして、抜群の政治力で今川家の内紛を収めた伊勢新九郎。



有難う!
駿河の東の興国寺城を差し上げます!



有難き幸せ!
これで一国一城の主だ!
実は、この時、伊勢新九郎が守った「姉の子」が今川氏親であり、今川義元の父親です。



よしっ、興国寺城から、
伊豆へ、さらに相模へ!



そして、相模から
武蔵へ攻め込め!
抜群の軍事・政治センスを持っていた伊勢新九郎は、急成長しました。



最近、急成長している
伊勢って何者?



さあな、伊勢という名前だから、
伊勢国の人じゃないか?



なら、俺たち関東の
人間には関係ないな・・・
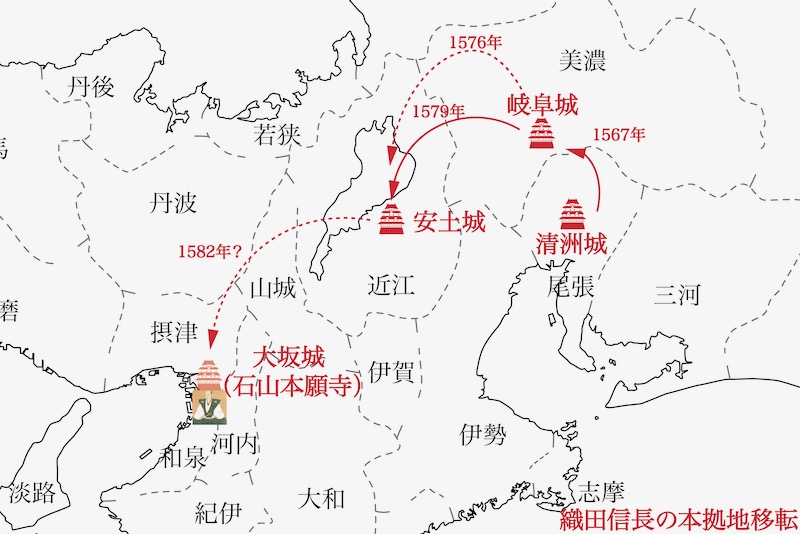

旧国名にある「伊勢」は、現代でも「伊勢海老」などの名称で残っています。



これでは、我らは
「よそ者」扱いだ・・・
悩んでいた伊勢新九郎は、新九郎の子で二代目氏綱の時に、「北条に名前変更」しました。(諸説あり)
そして、初代・伊勢新九郎は北条早雲という名前に変わりました。
Daimyo_G105tsなぜ「北条」という名前にしたかというと、「親戚が北条さんだった」などではありませんでした。



鎌倉幕府執権・北条と
同じ名前ならば・・・



関東の国衆たちにも
馴染みがあり、支配しやすいだろう・・・
鎌倉幕府の執権・北条氏に「勝手にあやかった」のが実態でした。
Daimyo_G106ts
そのため、鎌倉幕府執権の北条氏と、戦国時代の北条氏は「全く無関係」です。
区別するために、後の北条氏を「後北条(ごほうじょう)氏」と呼ぶこともあります。


そして、もう一人の国衆出身の大大名・毛利家は、幕末に長州藩として大きな影響を及ぼしました。
この意味では、「下位の家格」とも言える国衆は、日本の歴史に甚大な影響を与えたとも言えます。
次回は上記リンクです。


